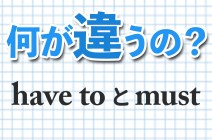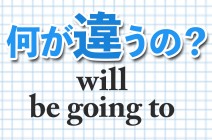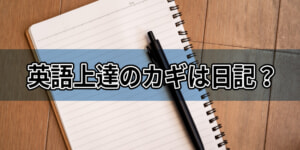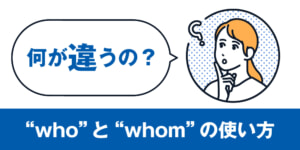英語の使役動詞make, let, have, get意味と使い分け!

英語を学んでいると「使役動詞」が出てきますよね。
数が多く、日本語では「~させる」と訳すため、使い分けに悩む人も多いでしょう。
そこで今回はよく使われる使役動詞4つの意味と使い分けについて解説していきます!
【こんな方に読んで欲しい】
- 使役動詞の使い方が知りたい
- 使役動詞のよく使う語句を覚えたい
- そもそも使役動詞がよくわからない
QQ Englishでは、公式ラインアカウントにて「英語に関する情報・お得なキャンペーン情報」を配信しています。この機会にぜひ登録を!
使役動詞
英語では「make, let, have, get」の4つが主な使役動詞と言われています。
基本的な使い方は、以下の通りです。
主語 使役動詞 人/物 (してもらう)動作や状態
「人/物」が意味上の主語となり、「人/物を使って何かをさせる」という意味になります。
どれも「〜させる」という意味を持ちますが、状況や意味合いによって使い分けが必要です。
その状況や人の立場、例文を踏まえながら丁寧に解説していきます。
この記事を読み終わる頃には使役動詞がよくわかっているでしょう!
make
makeを英英辞典(ロングマン)で引くとこのように出てきます。
“to force someone to do something”
“force” とあるように、無理やりにでもやらせるのがmakeを使った使役動詞です。
makeは元々が「作る」という意味ですから、そもそもの形を変えてしまうニュアンスが強く出ます。
【主語+make+人+動詞の原形】で「強制的に~させる」という意味です。
逆らえないような強さをはらみます。
自分の気持ちに反して何かをさせられる、せざるを得ない場合が多いです。
相手の希望に応じる時や許可する時には使いません。
- My boss made me work overtime yesterday. (昨日は上司に残業させられた。)
- My son’s smile makes me happy. (息子の笑顔が私を幸せにする)
一つ目の例文では、上司に強制的に残業をさせられています。
本当は残業したくなかったけど、せざるを得なかった」というニュアンスです。自分の意志は関係ないためmakeがきます。
二つ目の例文では、幸せになりたいと思って幸せになるのではなく、息子の笑顔で意志に関係なく幸せになるのmakeになります。
let
letを英英辞典で引くとこのように出てきます。
“to allow someone to do something”
“allow” とあるように、何かすることを許可をするのがletを使った使役動詞です。
Let’sも ”Let us” の略ですから、使役の中でもお手軽な印象があります。
【主語+let+人+動詞の原形】 で「~することを許す・許可する」という意味です。
「もしよかったら〜してください。」のように相手に判断を委ねるような使役です。
許可を求めたり、要求したりする際に使います。
- My boss let me go home early today because of sickness. (病気のため、上司は早めに家に帰してくれた)
- Let me know if you need my help. (助けが欲しいときは知らせてください)
一つ目の例文では、早く帰りたい自分のために上司がLetでその許可をくれています。
上司は私に判断を委ね、私はそれに従った行動を取った形です。
二つ目の例文は、命令文なので主語のYouが省略されています。
助ける準備はできてるから、必要になったらknowという状態にしてね、というニュアンスです。
この「Let me 動詞.(私に~させて。)」という表現はよく使われます。
私が~することを許可してねから派生して私に~させてとという身になっています。
have
haveを英英辞典で引くとこのように出てきます。
”to persuade or order someone to do something”
“persuade”とあるように、何かを要求する際に使う使役動詞です。
動詞の ”persuade” は行動する理由や義務などを考えさせるニュアンスも含んでいます。
【主語+have+人+動詞の原形】 で「義務や仕事として~させる」という意味です。
このhaveは「make」と似た様な意味ですが、「make」よりも強制度は低いです。
基本的には、立場的にしてもらって当然の事をしてもらう、というニュアンスになります。
例をあげると、上司が部下に指示を与えて仕事をさせる場合や、お客さんが店員さんに何かをしてもらうような場合、「させられる」側はそれが当然と思っています。
それがhaveのニュアンスです。 makeとの違いは「させられる」側がその行為を納得して行うか、意志にかかわらず強制的にやらせるかになります。
- I had him make the presentation for next meeting. (彼に次の会議用のプレゼンテーションを作らせた)
- I’ll have her call you back. (彼女に電話をかけなおさせます)
一文目のhim(彼)はプレゼンテーションが必要な資料の責任者か何かでしょう。
彼が資料を作成するための情報を持っていたり、適任であったりするニュアンスがあります。
そのため業務としてやらなければいけないことだと認識して行っているのでhaveが使われます。
二文目は会社などでよく使われる表現です。
クライアントから電話がかかってきたが担当者が不在だった場合、「かけなおさせます」と言う場合に使われます。
get
haveを英英辞典で引くとこのように出てきます。
“to persuade or force someone to do something”
先ほどのhaveと同じpersuadeですが “or force” が含まれています。
have よりは make に近いニュアンスです。
【主語+get+人+to不定詞(現在進行形)】 でmakeと同様に「強制的に〜させる」という意味です。
- We couldn’t get him to sign the agreement. (彼に契約を合意させることができなかった)
- In the end, we got the children clearing the playground. (最後には子どもたちに遊び場をキレイにさせました。)
一文目では契約内容に納得いただけなかったのでしょう。
納期やノルマがギリギリで、どうしてもサインさせたかったのにできなかったニュアンスを含んでいます。
二文目では、優しくお願いしたと言うより、強く叱ったニュアンスがあります。
「使ったらお片付けしましょうね」というよりも「何をしたらこんなに散らかすの?片づけなさい!」というイメージです。
優しく片付けてねという場合は ”ask” などを使ってお願いする表現を使うでしょう。
まとめ
今回は主な使役動詞を4つ紹介しました。
使役動詞は単語の選定次第で「強制」など強い印象を与えてしまいがちな表現です。
ぜひ適切な使い方をできるように覚えておいてくださいね。
では、最後にmake, let, have, getの意味を再確認します。
- make:強いて~させる
- let:~することを許す・許可する
- have:義務や仕事として~させる
- get:強制的に~させる
使い方を覚えて正しい表現ができるように練習しましょう!
関連記事:合わせてチェックしよう!
>>使役動詞を使えば英会話の幅が広がる!4種類総まとめ
>>こんな時に役立つ!!便利な性質をもった動詞を知っていますか?!