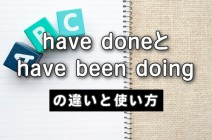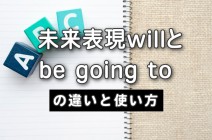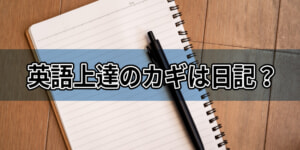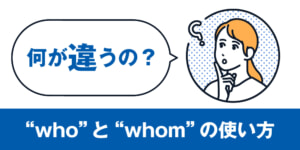canの本当の意味とbe able toとの違い、英会話での使い方をご紹介します

皆さんはcanとbe able toの意味や、使い方の違いを正しく説明することはできますか。
学校で勉強した際に、どちらも「〜できる」と習った記憶や、両方とも同じと覚えている方もいるのではないでしょうか。
日本語もそうですが、形が違えば意味も違うのが言葉の基本です。一見、同じように習ったこのcanとbe able toも、詳しく理解するとニュアンスや、使い方が異なっています。
今回は、そんな詳しく知らなかった「違い」についてちょっと掘り下げていきましょう。
canの本当の意味とは
英語を勉強している人なら当然、このcanの単語の意味はご存知ですよね。そうです、この単語は「助動詞」であり、「〜できる」という意味です。
ですが、実はその「〜できる」という意味にはさらに細かいニュアンスも含まれています。
「隠れた能力」
実は、助動詞のcanにはこの「隠れた」、「潜在的」という意味合いを含んでいます。
助動詞を勉強した際に、「能力」や「可能性」、「推量」、「許可」といった違った使い方があると勉強した方も多いと思います。
ですが、これらの使い方の違いもすべて、この「潜在的」な性質で説明することができます。
例えば、同じcanでも、
You can use my car.(僕の車使っていいよ!)
It can’t be true!(ありえない!)
など、様々な使い方ができますよね。
①は「能力」としての使われ方、
②は「許可」としての使われ方、
③は「推量」としての使われ方をしていますね。
どの表現にも、「潜在的な性質」としての「〜できる」という意味合いが含まれていることを感じ取れましたか。
①では、その彼女がピアノを弾けるという「性質」を持っている。②では、話しかけた相手が車を使用していいという「性質」を持っている。
③では、itに当てはまる対象が、その「性質」を持っていないことから「ありえない」という意味になっていますね。もちろん、この性質は過去形であるcouldになってもそのまま引き継がれます。
このcanの「助動詞」であることと、「秘めた性質」、という点は、次に説明するbe able toとの使い方に大きな違いを生むので、ぜひ覚えておきましょう。
be able toとは
be able toは、形容詞であるable「〜できる」に、to不定詞で何ができるかの情報を付け足している形です。
つまり、「〜ができる状態にある」という表現になります。
形容詞ableの「〜ができる能力がある」が重要です。先ほど説明したcanには、「秘めた性質」という意味合いが含まれているとお話しましたが、このbe able toにはそのような意味合いはなく、単に「〜ができる」という意味があるととらえておきましょう。
それでは、例文を見てみましょう。
I was able to fix my computer.(パソコン直せたよ。)
I’ve always wanted to be able to speak English.(英語がずっと話したかった。)
be able toを使用して文を作ると、このようになります。それでは、どのような場合でどちらの表現を使えばいいのか、場面ごとに見ていきましょう。
現在形、過去形を使う時
現在形、過去形を使う時は、基本的にどちらを使用しても文法的に間違いはありません。
しかし、大事な注意点があります。
日常的な会話の際には、断然canの方が優先的に使用されるので、be able toをあえて使用すると、「〜ができる」という意味を全面に出しているので、すごく強調された表現になります。
先ほどの「ピアノが弾ける」という例文で違いを見てみましょう。
She is able to play the piano.(彼女、ピアノ弾けるよ。)
どちらも日本語的には同じですが、話者の気持ちの違いが感じ取れますね。
この文が、同じ文脈で言われたとすると、①の文では単に彼女がピアノを弾けるということを言っているのですが、②の文では、「~できる」が強調されているので、聞き手が「最近弾けるようになったのかな?」や、「ピアノが弾けなかった理由があって、今はそれがなくなったのかな?」など、推測してしまう表現です。
「〜ができる」ということを強調したい場面はbe able toを使い、それ以外はcanを使うようにしましょう。
to不定詞と使う場合
to不定詞とは、toと動詞の原形で「〜すること」、「〜するために」と言うことができる表現方法ですが、to不定詞と使う場合は、必ずbe able toが使われます。
理由は簡単で、to不定詞のtoの後ろは「動詞の原形」が来る必要があり、canは助動詞のため使用することができません。
ですので、動詞のbeが使われているbe able toを使います。
この文は、to不定詞を使用していますので、I want to can〜とはなりません。to不定詞と一緒に使う時はbe able toと覚えておきましょう。
他の助動詞と使う場合
助動詞はcan以外にもたくさんあります。他の助動詞と「〜できる」を一緒に使いたい場合は、be able to を使用します。
「〜かもしれない」というmayとcanの「〜できる」は一緒に使用することはできないので、例文のようにmayの後ろにbe able toを入れて「〜できるかもしれない」という表現をすることができます。
mayだけではなく、willやshouldなどの他の助動詞でも同じです。
実際に何かを「やり遂げた」時
canとbe able toの使い方で、大きな違いが出る表現の一つがこちらのテーマです。例えば、パソコンが壊れていて、それを修理しようとしたとしましょう。
その場面では、canとbe able toを使って二つの言い方ができますね。
I was able to fix my computer.(コンピューター直せたよ。)
これ、日本語にするとどちらも同じに聞こえますが、意味合いが違います。
canのイメージである「秘めた性質」を覚えていますか。
canを使った①の文では、「私はコンピューターを直すことができる(という能力がありました。)」という文になっているのです。
これを使う場面として、上の例文の状況に当てはめてみるのであれば、例えば、「コンピューター壊れちゃったんだけど、機械あんまり分からないから新しいの買っちゃった。」というコメントに対して、①の文で「I could fix your computer. (君のコンピューター直せたよ。)」というと、「実際には直していないけどその能力はありました。」という言い方になりますね。
これに対して、②の文は、「直せる能力があり、実際に直した」という場面で使用されます。
be able toが「~できる」という気持ちを全面に出す表現だったことを覚えていますか。「〜できる」を全面に出す、つまり「実際にやった」という表現になります。
ですので、こちらの例文、パッと見ると同じ事を言っているようにも見えますが、①は「~できた(けどやったとは言いていない)。」、②は「〜を実際にやり遂げた」という気持ちの違いがあります。
ですので、「何かをやり遂げることができた」と言いたい時は、be able toと覚えておきましょう。
まとめ
ここまで、canとbe able toそれぞれを、場面別にどちらがふさわしいか詳しく掘り下げてみましたが、いかがでしたでしょうか。
普段の「〜できる」という何気ない会話では圧倒的にcanを使うことが多いです。ですが、上でも説明したように、ある特定の場面ではbe able toしか使えない場面もあります。
canは「秘めた性質」、be able toは「〜できる全面アピール」、この二つを意識して今日から英文に触れてみましょう。新しい発見があるかもしれませんね。