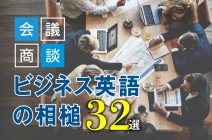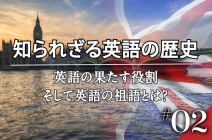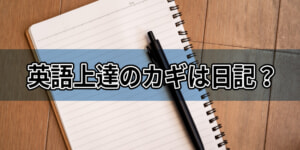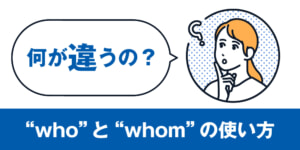【英語の歴史#1】なぜ世界には数多くの言語が存在するのか?

現在、世界でもっとも多く話されている言語といえば英語です。
英語を母語とする人の数は中国語を母語とする人の数には及ばないものの、公用語として英語を話す人、および外国語として英語を用いている人を合わせると、世界中で英語を話せる人の数は他のいかなる言語よりも圧倒的に多いからです。
その数は、約15億人といわれています。世界人口のおよそ四分の一の人が、英語を話せることになります。
英語こそが世界の共通言語であり、まさに国際語としての地位を不動のものにしています。
では、なぜ英語は世界の共通言語して認められるようになったのでしょうか?
英語が世界中に広がるまでには、実は壮大な物語が隠されています。
たとえば、そのひとつとして、ペスト菌のパンデミックをあげられます。
14世紀半ばに起きたペスト(黒死病)のパンデミックにより、ヨーロッパの人口の三分の一から二分の一が失われました。
現在の世界が新型コロナのパンデミックに襲われて右往左往しているように、当時のヨーロッパに暮らす人々も死の恐怖に怯えパニックに陥りました。
それが不幸な出来事であったことは間違いありません。しかし、ペストのパンデミックが言語史に大きな影響を与えたことも事実です。
もしペストのパンデミックが起きていなければ、英語が今日のように世界に広がることはなかったかもしれません。
このとき、何が起きたのかを含め、今回より英語の歴史について紹介します。
第一回目にあたる今回は、「世界の共通言語」にスポットを当て、世界にはなぜ多様な言語があるのかについて考えてみます。
1.バベルの塔と国際共通言語

ピーテル・ブリューゲルの描いた『バベルの塔』
https://ja.wikipedia.org/wiki/ より引用
かつて世界には、ただひとつの言語しか存在していなかったと伝えられています。
そのことは旧約聖書の創世記11章の1~2節で語られています。有名な「バベルの塔」の説話がこれです。
ノアの洪水によって世界が一度滅びた後、その子孫たちは世界各地に散るというノアとの約束を守ることなく、シナルの地に住み着いていました。
創生期には「全地は同じ発音、同じ言葉であった」と記されています。
ひとつの言葉しかなかったため、人間たちは容易に力を合わせ、高度な文明を築きました。その象徴となるのが「バベルの塔」です。
かつて神は自分に似せて人を創造したとき、アダムに向かって「生めよ。ふえよ。地を満たせ」と祝福しました。
ところが人はおごり高ぶり、「さあ、われわれは町を建て、頂が天に届く塔を建て、名をあげよう。われわれが全地に散らされるといけないから」と、あたかも神に挑むかのような態度を見せたのです。
これに怒った神は、「彼らがみな、一つの民、一つのことばで、このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことで、とどめられることはない。さあ、降りて行って、そこでの彼らのことばを混乱させ、彼らが互いにことばが通じないようにしよう」と、介入を始めます。
その結果、言語がバラバラになったために共同作業ができなくなり、バベルの塔の建設は挫折に追い込まれます。
言語が異なる同士が一緒に暮らす意味もないため、やがて人々は世界各地に散っていくことになるのです。
この説話の面白いところは、神がバベルの塔を破壊しようと思えば簡単にできたはずなのに、そうはせず、ひとつだった言語を複数に置き換えることで、人間界を混乱におとしめたことです。
もともとひとつだった言語が複数に分かれるだけで、人々は意思の疎通ができなくなり、文明の発展も止まったわけです。
現在も世界にはさまざまな言語があります。三省堂の言語学大辞典・世界言語編では8000超の言語が扱われています。
では、逆に今の時代に、世界のどこに行っても通じる共通言語があったとすればどうでしょうか?
そのとき、人類は共通言語を介することで固く結びつき、文明をますます発展させ、善し悪しはともかく全知全能の神に並ぶほどの叡智(えいち)を身につけられるのかもしれません。
世界の共通言語は、人類にとってのロマンです。
実際のところ、19世紀にはそうした試みが複数為されていました。そのなかでもっとも有名なのは、ルドヴィコ・ザメンホフとその弟子たちが考案した「エスペラント語」です。
人工言語であるエスペラント語は、共通の母語を持たない人々の間で意思伝達をするために使われる国際補助語として、もっとも成功した言語です。
しかし、エスペラント語を公用語とする国は現在ではひとつもありません。エスペラント語をはじめ、人工的な国際共通語を広めようとする運動は、今日まですべて失敗に終わっています。
結局のところ、現状から考えて国際共通語にもっともふさわしいのは「英語」と言って間違いなさそうです。
それにしても言語を統一することは、どうしてこうも難しいのでしょうか?
2.かつて日本でもあった「英語国語化論」
世界中をひとつの言語に完全に統一するためには、その国や地域で元々使われていた言語を廃止する必要があります。
そんなことが果たして可能でしょうか?
実は母国語を外国語に置き換えるべきか否かをめぐり、真剣に議論された国があります。他ならぬ日本です。
日本語を廃止し、英語を国語にしてしまおうとする動きが過去に何回かありました。主として明治初期と終戦直後には、盛んに議論されています。
小渕恵三内閣のもとで2000年1月に「21世紀日本の構想」のひとつとして「英語の第二公用語化」が取り上げられましたが、「英語国語化論」のインパクトは、その比ではありません。
日本語に加えて英語を第二公用語にするどころか、日本語そのものを廃し、英語を母国語に据えようとするわけですから半端ありません。
「英語国語化論」は、初代文部大臣となった森有礼(もり ありのり)によって主張されました。森がそのように考え、一定の支持を得たのは、明治初期という時代が大きく影響しています。
日本周辺のアジア諸国が次々と欧米に侵略され、植民地化されるなか、軍事を含め学術レベルを一気に世界標準に上げなければ、日本もまた欧米各国の植民地となる定めにありました。
欧米に追いつくためには、日本語を捨ててでも英語を国語とし、欧米の先進的技術や知識を吸収するよりないと考えたのです。切羽詰まったなかでのやむを得ない選択でした。当時は福沢諭吉も、英語による国語教育を主張しています。
しかし、「英語国語化論」は多くの反対を受け、実現には至っていません。
そればかりか森は「英語国語化論」によって西洋かぶれと見なされるとともに、日本の伝統文化を毛嫌いする傾向があるとの烙印を押され、43歳の若さで国粋主義者の手にかかり暗殺されています。
この一件は、現在使われている言語を廃し、何らかの外国語に自発的に置き換えることがどれだけ難しいかを、物語っています。それを口にしただけで命まで狙われたのでは、たまったものではありません。
ちなみに今日から振り返れば、森たちが危惧したような事態は起こらなかったことがわかります。
国語を日本語から英語に置き換えなくても、日本は軍事においても科学においても、あっという間に欧米に追いつき、追い越すという奇跡を成し遂げ、欧米の植民地になることを免れています。
その理由は、明治初期の知識人たちが、あらゆる学問にわたって精力的に翻訳を成し遂げたためです。
そのため日本人は、日本語を通して世界最先端の技術や知識を吸収できました。新たな学術用語もどんどん作られ、日本語は拡張されたのです。
もとは外来語である漢語と日本古来の大和言葉が合体してできた日本語は、新たな外来語を容易に作り出せる言語であったことも幸いしました。
自国語のみだと柔軟性に欠けるため、造語をひねり出すのも簡単ではないようです。たとえば中国語です。中国語は外来語を漢字に置き換えることを苦手としました。
一方、明治時代に造られた和製漢字のレベルは高く、中国に逆輸入されています。その数は膨大で、「現代の中国人は日本由来の漢字を使うことなく会話はできない」とまで言われています。
中国の正式な国名である「中華人民共和国」にしても、「人民」と「共和国」は日本から逆輸入された言葉です。
「歴史・文化・革命・電気・電話・電車・自転車・病院・警察・時間・温度・哲学・法律・主張」等々、数多くの和製漢字が中国で今もそのまま使われています。
これから紹介する英語の歴史においても、外来語は大きく影響しています。
森有礼亡き後も、日本語を外国語に置き換える案は、浮上しては消えました。
終戦直後には小説家の志賀直哉が「フランス語を国語にせよ」と唱え、議会政治の父と呼ばれる尾崎幸雄が日本に民主主義を根付かせるためには、日本語をやめて英語を国語にすべきだと主張しました。
尾崎幸雄は慶應義塾にて福沢諭吉から学んでいることも、影響しているのかもしれません。
それとは別にGHQによる漢字廃止の動きがありました。連合国は漢字を民主化の敵と捉え、日本語の表記から漢字をすべて廃し、ローマ字に置き換えようとしました。
「一億玉砕」や「国民特攻」などの日本独特の危険思想が生まれたのは、漢字が難しいために文字を読める国民が少なく、一部の指導層の言いなりになったからだと分析したためです。
もし、このとき漢字が廃され、すべてをローマ字で表記するように改められていたならば、現在の日本とはかなり異なる国が生まれていたに違いありません。
GHQは漢字を廃止するための一環として、日本全国の15歳から64歳までの1万7千人を無作為に選び、漢字の読み書きテストを実行しました。
ところが、GHQの意に反する驚きの結果がもたらされます。
漢字の読み書きができない人は、わずか2.1%にすぎなかったのです。つまり日本の識字率は97.9%になります。これは日本の教育レベルの高さを示す数字です。
こんな高い識字率を示す国はどこにもありません。さすがにGHQも漢字廃止をごり押しすることをあきらめ、日本語は生き残りました。
しかし、その後も漢字廃止の動きは繰り返されました。その理由は、ローマ字であれば英文タイプライターによって素早く文字に起こせることに対し、漢字の入った文章を印刷するためには、複雑な工程を必要としたためです。
これを解決したのは、技術の進歩です。1978年、東芝が世界初となる日本語ワープロ JW-10 の販売を始めたことで、はじめて漢字交じりの文も素早く生成できるようになったのです。
ちなみに、このワープロの料金はいくらだったと思いますか?
なんと、630万円です。今ではパソコンやスマホで簡単に日本語を打つことができますが、当時にしてみれば、まさに夢のような技術だったといえそうです。
日本語が消滅する危機は幾たびかあったものの、日本語を存続させようとする力の方がはるかに強く、今日まで日本語は受け継がれています。
なぜならば、言語とは民族にとっての精神そのものであり、まさに魂そのものだからです。言語という魂を失えば、民族は民族でいられません。
ルーマニア人の思想家、エミール・シオランは、こう言っています。
「人は、国に住むのではない。国語に住むのだ。『国語』こそが、我々の『祖国』なのだ。」
祖国を祖国たらしめているのは、文化や伝統・歴史であり、その地で育(はぐく)まれてきた情緒です。それら一切は、言語のなかに息づいています。
その意味では言語こそが祖国です。言語が失われれば、祖国が失われるも同然です。
それこそが、世界に多様な言語が存在する理由といえそうです。
今、私たちたちに必要なことは固有の言語はしっかり保持しながらも、それとは別に国際共通語として機能している英語を、コミュニケーションの道具として活用する力を身につけることです。
次回は、現代の世界において英語がいかなる役割を果たしているのかを、改めて考えてみます。