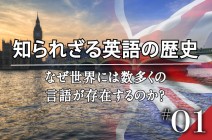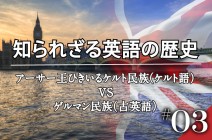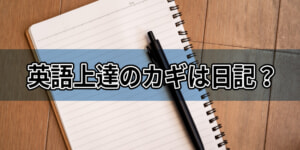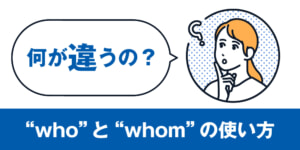【英語の歴史#2】もともと英語は北ドイツの小さな部族で使われていただけだった!

前回は、世界にはなぜ複数の言語があるのかについて考えてみました。
→【英語の歴史#1】なぜ世界には数多くの言語が存在するのか?
今回は国際共通語として英語の果たす役割を整理するとともに、英語の歴史をたどる上で欠かすことのできない英語の祖語についてさかのぼってみます。
1.英語に課せられた国際共通語としての役割
国際共通語の歴史をさかのぼってみると、まずは中世ヨーロッパのラテン語に行き着きます。中世ラテン語は、ローマ帝国の標準言語であった古典的ラテン語から変化した言語です。
中世のヨーロッパであれば、どの国であろうとも、官職や教会の職に就く人や学者であればラテン語だけをマスターしておけば、事足りました。
東アジアであれば漢語が国際共通語に近い言語でした。しかし、漢語はあくまで書き言葉としての共通語としての役割は果たしたものの、話し言葉としては活用されていません。
そのため、中世ラテン語こそが国際共通語と呼ぶにふさわしい言語といえます。
やがて宗教改革が起きるとラテン語の聖書しかなかった状況が覆り、ドイツ語やオランダ語、英語やフランス語の聖書が登場したことにより、ラテン語は次第に国際共通語としての力を失っていきました。
ラテン語に代わって国際舞台(外交)で重んじられたのはフランス語です。
フランスは「ローマ帝国の長女」と言われるほどに完全にローマ化した過去があり、フランス語のボキャブラリーはラテン語によく似ていました。ラテン語からシフトするには、フランス語は適した言語だったのです。
第一次世界大戦後には、エスペラント語を中心とする人工言語が登場し、国際補助語に据えようとする運動が起きたものの失敗に終わったことは、すでに紹介しました。
やがて第二次世界大戦後にアメリカの国力が傑出するとともに、国際共通語としての地位を固めていったのが英語です。特定の分野に強かった各言語を、戦後は英語が圧倒するようになります。
たとえば、戦前は科学の面でドイツ語が世界をリードしていました。
ことに医学においては、ドイツこそが世界最先端でした。戦前の日本人はドイツ語で医学を学びました。そのため、当時は日本の医者がドイツ語でカルテを書くことも一般的でした。
しかし、ドイツが戦争に敗れたこともあり、ドイツの優秀な科学者や医学者の多くはアメリカへ渡り、研究活動を続けました。
これにより、科学や医学の最先端はアメリカへと移り変わり、ドイツ語がわからなくても英語さえわかれば、それらの技術や知識を身につけられるようになったのです。
現在では専門用語の大半は英語をもとにしています。
ノーベル賞の数を見ても、アメリカやイギリスという英語圏の出身者が圧倒的に多いことは事実です。
現在では科学にしても医学にしても、研究者の国籍にかからわず論文のほぼすべてが英語で書かれています。重要な国際会議やセミナーにしても、英会話が用いられます。
あらゆる学問にしても、世界最高峰のプログラムが用意されているのは英語圏に偏っています。英語ができれば、最高の学問を習得するチャンスも増えます。
学問を離れ、ビジネスにしても、英語は国際共通語としての役割を果たしています。コロナ禍により一時的に国際貿易の規模が縮小しているとはいえ、取引国が増え、やがて拡大に転じるのは間違いないだけに、今後も英語の需要は高まる一方です。
母語が異なる同士がコミュニケーションをとるためには、両者が知っている最大公約数の言語を用いることが理に適っています。
世界の四分の一の人々が使うようになった英語が、世界の最大公約数の言語であることは間違いありません。英語の裾野が今後拡大することはあっても、縮むとは考えにくい状況です。
多国籍企業のほとんどが人材募集の際に、一定の英語力があることを条件としています。大企業で働くために、今もこの瞬間に世界中の多くの人々が英語を学んでいることも、英語の裾野を広げることに一役かっています。
国家間の利益が衝突する通商・外交の分野でも、英語は国際共通語として用いられています。英語は国連や北大西洋条約機構(NATO)、世界銀行(World Bank)や国際通貨基金(IMF)の公用語です。
また、石油輸出国機構(OPEC)では加盟国13カ国はいずれも英語を母語としていませんが、唯一の公式言語として用いられているのは英語です。
航空や海洋上の交信の際にも、英語は不可欠です。たとえば日本国内でパイロットと管制官が日本人同士であったとしても、英語で交信を行うことが原則となっています。ごく一部の例外を除き、世界中どこへ行っても同じ状況です。
スポーツや娯楽の分野でも、英語の一人勝ちが続いています。
オリンピックの公式言語は英語とフランス語です。第一公用語がフランス語になっているのは、近代オリンピックの生みの親であるピエール・ド・クーベルタン男爵がフランス人であることに対する敬意からです。
観衆の規模としてはオリンピックを凌ぐサッカーのワールドカップの公式言語は、英語を含めた四カ国語です。ことにレフェリーの公式言語は英語のみです。
映画は大半が英語で占められています。
世界で上映される映画の8割以上で英語が用いられていると言われています。ポップミュージックも同様で、世界レベルのミュージシャンの大半は英語で活動しています。
このように、今日の世界において英語は国際共通語としての役割を見事に果たしています。
それにしても、考えてみれば不思議なものです。
もともと英語は、北ドイツの小さな部族で使われていただけの弱小にすぎない言語でした。
その英語が、どうやって国際共通語にまでのし上がったのでしょうか?
そこには、偶然と必然が織りなす興味深い物語があります。まずは英語の元になった言語にさかのぼって追いかけてみます。
2.英語の祖語をさかのぼる
旧約聖書に出てくる「バベルの塔」について、前回ふれました。聖書の世界では、もともと人類はただひとつの言語を使っていたとされています。
一方、宗教を離れた純粋な学術面からも、人類がはじめに単一の言語を使っており、その言語が枝分かれすることで、さまざまな言語が生まれたとする学説があります。
たとえば「ノストラティック仮説」です。20世紀初頭にデンマークの言語学者ホルガー・ペデルセンが唱えた「ノストラティック仮説」は、氷河期の終わる頃の紀元前15000年から紀元前12000年前にかけて話されていた、世界で唯一の原始言語であったとされています。
「ノストラティック」はラテン語の nostrās に由来し、「同胞」の意味です。
「ノストラティック仮説」は旧ソ連邦で支持されたものの、西側の学者には懐疑的とみなされ、荒唐無稽な珍説と受け止められました。
しかし、人類が単一の言語を起源とする説は、あながち間違っていないかもしれません。なぜなら近年、遺伝学的な研究が進んだことにより、「現生人類単一起源説」が確定的となったためです。
人類の起源をめぐっては、2つの学説が対立していました。人類の起源がアフリカにあることは、もはや常識です。問題はそのあとです。
アフリカを出た人類は多くの地域に散らばりました。
たとえば北京原人やジャワ原人について学校で習った記憶を持つ人は多いことと思います。多くの地域で進化を遂げることで、今の人類に進化したと考えるのが「他地域進化説」です。
1980年代後半までは、この「他地域進化説」が有力とされていました。ところがミトコンドリアDNAの分析により、この説は間違っていたことが今日でははっきりしています。
現在のすべての人類は、約20万年前に生存した、たった一人のアフリカ女性の子孫であることがわかったためです。
いわゆる「ミトコンドリア・イヴ」です。アフリカを出た人類を含め、その他の人類はすべて絶滅したため、現代人につながる子孫を残してはいません。
現在の私たち人類が、すべて一人のアフリカ女性を祖先にもつ以上は、人類の言語がもともとひとつであったとするほうが合理的です。
このような考え方は言語学の世界では異端扱いされていますが、今後の研究が進めば塗り替わるかもしれません。
単一ではないものの、世界の言語が複数の祖先をもつグループに分かれていることは、すでにわかっています。このグループのことを「祖語」と呼びます。
紀元前4000年頃、現在のウクライナの辺りに共通の言語を話す集団がいました。その言語は「インド・ヨーロッパ祖語(印欧祖語)」と呼ばれています。
その集団は数千年の時をかけながら、西はヨーロッパ、東はインドへと散らばっていきました。長い時間のなかで、それぞれの地域ごとに印欧祖語は次第に変化しました。
そうして枝分かれしたひとつが「ゲルマン語派」です。「ゲルマン語派」がさらに枝分かれすることでドイツ語やオランダ語、そして英語が生まれています。
一方、「ゲルマン語派」と並ぶように「イタリック語派」があります。「イタリック語派」がさらに枝分かれすることでラテン語やフランス語、スペイン語、イタリア語などが生まれました。
印欧祖語から枝分かれすることで、他にも多くの言語が誕生しています。ロシア語やペルシャ語なども、その一部です。
こうした言語の系統樹を見渡すことで、英語とドイツ語やオランダ語がかなり近い言語であること、フランス語やロシア語なども同じ印欧祖語に属すものの、実際にはかなり遠い親戚であることがわかります。

「歴史で謎解き!フランス語文法 第18回 なぜ英語とフランス語は似ているの?」より引用 https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/ghf18
言語の系統樹からは、英語とドイツ語が極めて近い言語であることがわかります。
それは、なぜでしょうか?
次回は、この謎を追いかけてみます。