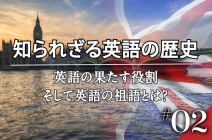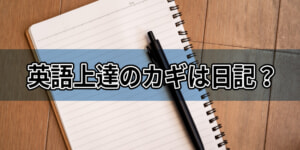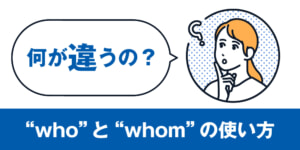【英語の歴史#3】アーサー王ひきいるケルト民族のケルト語 VS ゲルマン民族の古英語

前回は英語の祖語について紹介しました。
→ 【英語の歴史#2】もともと英語は北ドイツの小さな部族で使われていただけだった!
今回から、いよいよ具体的な英語の歴史についてたどってみます。
1.English の由来とは
英語という言語が使われ出したのは、およそ1500年ほど前のことです。
アングル人、サクソン人、ジュート人などのゲルマン小民族の間で話されていた言語が英語です。いわば英語は、ゲルマン語のなかのひとつの方言にすぎない言語でした。
彼らが住んでいたのはブリテン島(イングランド)ではありません。ヨーロッパ大陸のデンマークから北西ドイツおよびオランダに居住していました。これらの地こそが英語の故郷です。
ブリテン島にはすでに先住民が住み着いていました。
有名な巨石遺跡ストーンヘイジは紀元前3000年から紀元前2000年にかけて建てられたものです。巨石遺跡を造れるほどの文明が、すでにその当時から栄えていたと考えられます。
その後、紀元前1000年頃にヨーロッパ大陸からブリテン島に渡来したのはケルト系民族です。彼らの言語はケルト語です。
やがてイングランドとウェールズにあたる地方がローマ帝国の支配を受けますが、ゲルマン人の大移動によって帝国が衰退したあと、アングル人やサクソン人などのゲルマン系民族(いわゆるアングロ・サクソン)が449年にブリテン島へと押し寄せ、先住民族であるケルト人から土地を奪っていきました。
この449年が、英語史において英語の始まりの年とされています。
英語史では、英語を大きく三つの時期に分けています。450年から1100年頃までを「古英語」、1500年頃までを「中英語」、それ以降が「近代英語」、そして「現代英語」へとつながっています。
ケルト系民族もアングロ・サクソンの侵略に必死に抗いました。
「アーサー王伝説」は、このときに生まれたものです。ケルト系のブリトン人であったアーサー王は、侵入したアングロ・サクソンを幾たびか撃退した英雄とされています。
それでもアングロ・サクソンの勢いを削ぐことはできず、600年頃までにはアングロ・サクソンがブリテン島の大部分を支配しました。ケルト系民族は西方(現在のスコットランド、ウェールズ、アイルランド)へと追いやられています。
ケルト人は、この新たに押し寄せてきたゲルマン民族のことを総称として「アングル人」と呼びました。English や England に見られる Engl-という言葉は、 Angle に由来しています。アングル人の言葉が English、アングル人の土地が England です。
2.古英語と現代英語の違いとは
ブリテン島を征服したゲルマン民族の言語であった古英語は、ドイツ語の一つの方言と捉えられています。そのため、現在のドイツ語と似ており、共通点がたくさんあります。
よく、ドイツ人は古英語から入った方が英語を理解しやすいと言われるのは、そのためです。
ドイツ語を習うと必ずといってよいほど苦労するのが、名詞の性です。ドイツ語の名詞には男性・女性・中性の3つの性が割り当てられており、覚えるのが大変です。実は古英語の名詞にも、3つの性がありました。それだけでも、現代英語よりかなり複雑になります。
さらに古英語では、名詞・形容詞・動詞は、文のなかで果たす役割に応じて語形変化しました。たとえば現代英語でも、三人称・単数の主語を用いて現在の時制における行動・状態をあらわす英文には、動詞に“s”をつけますよね。
He plays soccer. (私はサッカーをします) の “plays” が、これです。これを「3単元のs」と呼びますが、なぜ “s” を付けなくてはいけないのか不思議に思ったことはありませんか?
「理屈よりも丸暗記することが大切だ」とよく言われますが、「なぜ」がわかったほうが理解が進むことも事実ですよね。
実は古英語では「3単元」に限らず、I であっても we であっても you であっても、何かしらの語尾が付いていました。古英語が長い年月をかけて変化するなかで、複雑な変化は次第に省略されました。
また、語尾が弱い音だった場合も、次第に消えていきました。結果的に残ったのは、発音がしやすくて語形変化が単純な “s” だった、というわけです。
古英語の時代から現代の英語まで残されている語形変化は、3単元のs・過去時制の-ed・過去分詞の-en・現在分詞の-ing・比較級の-er・最上級の-est・複数形のs・所有の-‘sの8つのみと指摘されています。
定冠詞も古英語では複雑でした。現代英語の定冠詞は the だけですが、古英語では名詞の性や文中での役割、単数か複数によっても変化するため、18ほどの定冠詞がありました。ちなみにドイツ語の定冠詞は16です。
不規則動詞が多いことも古英語の特徴です。現代英語では語尾に-edをつけることで規則変化する動詞が大多数ですが、古英語では write-wrote-written のように不規則に変化する動詞が多かったのです。
古英語における語形変化の複雑さは、現代英語をはるかに上回ります。その代わり、発音は現代英語よりも簡単でした。
古英語から中英語にかけては、綴り字のまま発音すればよかったためです。たとえば name の発音は古英語では「ナメ」です。見たまま発音すればよいだけに、現代英語のように不規則な発音はありません。
もっとも綴り字のままに発音するのは、それはそれで大変です。eight や right などの ”gh” は現代英語では発音しませんが、古英語では発音されていました。発音記号で表すと「x」の音です。
喉を鳴らすように h の音を出す発音ですが、なんとも発音しにくい音です。発音しにくいからこそ、自然に発音されなくなり、laughやenoughのように発音しやすい「f」の音に変化していったのです。
3.古英語は基本単語の宝庫
古英語のもう一つの特徴は、外来語がほとんどないことです。その意味では古英語は、日本語で言うところの「大和言葉」にあたります。大和言葉で綴られた古事記や万葉集には、外来語がほとんどありません。
とはいえ日本語は実は、古代と比べてもそれほど大きく変化している言語ではありません。1200年ほど前に書かれた『源氏物語』であっても、日本人であれば古文の授業で経験したように、古語を習いさえすれば原文を直接読んでも、ほぼ理解できます。
また、『平家物語』や『太平記』あたりになると大和言葉の比率がぐっと下がるため、現代人が読んでも意味を容易に把握できます。
しかし、古英語と現代英語の隔たりは大きく、英語圏の人が古英語で書かれた文を見ても、さっぱりわからないと言われます。英語と言うよりもドイツ語の感覚の方が強いためかもしれません。
それでもボキャブラリーを見てみると、誰もが知っているような単語の多くは、古英語にすでに含まれています。たとえば、make , do , have , hold , bring , open , get , home などです。
古英語は口語ベースの簡単な言葉が主体でした。そのため、シンプルな言葉が多く、数も最小限に抑えられていました。高度なコミュニケーションを図るよりも、生活に根ざした会話を成り立たせるための言葉が優先されたためです。
コンピュータ分析をしてみたところ、現代英語でもっとも一般的に用いられる基本単語100のすべてが古英語の時代に生まれていることがわかりました。
私たちが中学校で習う単語のほとんどは、古英語の頃から使われていたものです。英語圏に暮らす人々は今も、古英語の時代から生き延びてきた、こうした基本的な言葉を数多く組み合わせることで会話を行っています。
「中学英語を理解して使いこなせれば日常会話をこなせる」とよく言われるのは、そのためです。
4.地名に残るケルト語
一般的に征服された側の言葉は、征服した側の言葉には入りにくいものです。言葉には力関係が投影されています。
しかし、例外があります。地名については先住民の言葉をそのまま残しているケースが多いのです。
たとえばアメリカ大陸の先住民であったアメリカインディアンの言葉は、今の米語にはあまり残されていませんが、地名には多く残されています。アメリカ50州の半数を含め、多くの地名はインディアンの言葉に由来しています。
同じように、アングロサクソンによって西方に追いやられた被征服民族であるケルト人の言葉も、現在の英語にはあまり見当たりません。ですが、地名となると別で、古くから使われていた言葉がそのまま残されています。
イギリスの首都 London はケルト系の人名または部族名である Londinos(「剛勇の者」)に由来します。「テムズ川」の Thames はケルト語で「薄黒い川」の意味です。
また、スコットランドの「スコット」はケルト語で「漂泊者」を意味し、ケルト人を指す言葉です。一方、「ウェールズ」は古英語の名詞 wealh に由来し、「外国」を意味しています。アングロ・サクソン人から見て外国人の国だから「ウェールズ」と呼んだわけです。
ちなみにイギリスの正式名称は、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland です。訳すと「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」です。
イングランド・ウェールズ・スコットランド・北アイルランドの4つの国が連合することで単一主権国家を形成しているのが「イギリス」です。
そのため「イングランドの」を意味する「イングリッシュ」は、「イングランド」1カ国のみを表すため、4カ国すべてを併せた全イギリスを表すには不適切です。そこで使うのが、British です。
英国鉄道は British Railways 、英国陸軍は British Army 、英語は British English です。
ケルト民族とアングロ・サクソンの対立を軸に、4カ国の歴史的な葛藤が言語のなかに息づいています。
次回は、ヴァイキングの襲来によって古英語がどのような影響を受けたのかを確認しながら、ヴァイキングとアングロ・サクソンで繰り広げられた戦いの歴史について紹介します。