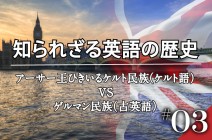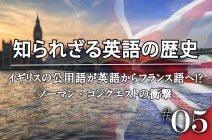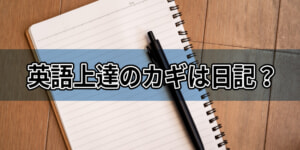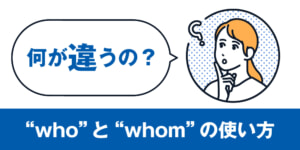【英語の歴史#4】ヴァイキング襲来!古英語はどう変化していったのか?

前回は English の由来について紹介したあと、古英語と現代英語の違いについて説明しました。
→ 【英語の歴史#3】アーサー王ひきいるケルト民族のケルト語 VS ゲルマン民族の古英語
今回はヴァイキングの襲来によって、古英語がどのような変化を遂げたかについて見ていきます。
1.ヴァイキング襲来による古ノルド語との融合
古英語が大きく変化するきっかけとなったのは、北欧に住むヴァイキングによる襲来を受けたためです。8世紀後半から始まったヴァイキングによるブリテン島への侵攻により、イングランドの半分以上が失われました。
このとき、イングランドの危機を救ったのが、アルフレッド大王です。
King Alfred the Great、あるいは the first king of England と呼ばれるアルフレッド大王は、侵入者であるヴァイキングと勇敢に戦い、多くの土地を奪い返しました。
アルフレッド大王のさらに大きな偉業は、ウェッドモア条約を結ぶことでヴァイキングの長をキリスト教に改宗させたことです。
これにより、その後に成立したヴァイキング王朝がキリスト教と対立することがなくなったため、ヴァイキングとアングロ・サクソンとが共存する道が開けたのです。
ブリテン島に侵入したのは、主としてデンマークのヴァイキングです。アングル人がブリテン島に来る前に、もともと住んでいた地はデンマークと隣り合っています。それだけに、言語も似ていました。
ヴァイキングが使っていたのは古ノルド語です。
古ノルド語は、デンマーク語・スウェーデン語・ノルウェー語・アイスランド語といった現代の北欧諸語の祖先にあたる言語です。
古英語も古ノルド語も、同じゲルマン語です。本質的な言語の違いは、方言の差程度でした。
もともとどちらもゲルマン人であり、先祖代々より暮らしていた地域が近かったために文化も似通っていたこともあり、ヴァイキングとアングロ・サクソンは次第に溶け合うようになりました。
それとともに、言葉の面でも変化が起こります。
古英語にしても古ノルド語にしても方言の差でしかないため、互いの言っていることは理解できます。しかし、語尾が異なるため、微妙なニュアンスになると誤解が生じ、しばしばトラブルの種になりました。
そこで、誤解が起きないように互いに複雑な語尾は削ぎ落としてしまおう、といった動きが起きたのです。
また、前置詞の使い方など、語感は同じなのに細かい違いがある箇所は、面倒だから省いてしまおうとする動きも高まりました。
こうして古英語独特の複雑な語尾変化は大量に削られ、規則的で簡単なものへと大きく変化しました。古英語が現代英語へ一歩近づいたことになります。
2.古英語に見られる古ノルド語からの借用
言葉の入れ替えも起きています。誤解を減らすために、古英語で発音が聞き分けにくい単語は、古ノルド語に置き換えられました。
代表的なのは、複数人称代名詞です。古英語では「彼らは」に hie 「ヒー」という単語を当てていましたが、「彼ら」を表す he 「へー」と聞き間違いやすいため、古ノルド語の they を使うようになりました。they 、 their 、 them は古ノルドから英語に入った言葉です。
前置詞と接続詞を兼ねる till も古ノルド語からの借用です。
このように代名詞や前置詞・接続詞などの文法要素にまで他の言語が影響を及ぼすのは、実はかなり珍しいケースです。
第1回目で日本語が外国の言葉を漢字に変換した上で借用したことにふれましたが、文法要素にまでは手を付けていません。
外国語からの借用は文法要素を抜かして行われるのが一般的なのです。ところが古英語は古ノルド語から文法要素まで借用しています。
このような例外的な動きが起きた理由は、ブリテン島でアングロ・サクソンとヴァイキングが、かなり密接な交流をしていたからだろうと推測されています。
古ノルド語からの借用は多岐にわたっています。古英語にはなかった観念とともに、それを表す言葉も入ってきました。ことに重要なのは、law(法律)です。
海賊として略奪を得意とするヴァイキングには「野蛮な民族」といったイメージが先行しがちですが、船を自由に操るためには一糸乱れぬ組織的な規律を必要としました。そのような秩序を表す言葉が law です。
欧州が他の地域に先駈けて文明国に成り上がる上で、 law は大きな役割を果たしました。その law の礎を築いたのは、実はヴァイキングです。
また、古英語と古ノルド語の両方の言葉が、現代英語にそのまま残っている例もあります。たとえば、否定するときに使う no や nay がそれです。no は古英語、nay は古ノルド語に由来します。
「技術」を意味する craft は古英語、skill は古ノルド語、「病気」は sick が古英語、ill が古ノルド系です。
それらのなかには、使うシーンが少しずつずれてくる言葉もありました。たとえば die(死ぬ)です。「死ぬ」という言葉は古ノルド語の die を使うようになったため、古英語で「死ぬ」を意味した steorfan を使う場面は限定され、現代英語では starve(餓死する)になりました。
want も古ノルド語から入ってきた動詞です。その意味は「欠く、持たない」を意味していました。当時は今とは異なり、 want に「欲する」という意味はありません。
しかし、人の性(サガ)として「持っていないと欲しくなる」という面が反映されることで、18世紀の初めにはwant に「欲する」という意味が与えられるようになりました。
こうした一連の古英語の変化は、アングロ・サクソンとヴァイキングが共存していた北の地域から始まり、次第に南下していきました。
これまで紹介してきたように、その特徴を一言で表せば、古英語から難しい語形変化が消え、文法が簡単になったことです。
簡略化されたことで、より便利となり、人から人へと新しい古英語は普及していったのです。
3.ヴァイキングとアングロ・サクソンの果てしなき戦い
アングロ・サクソンが建てた4つの王国のうち、すでに3つは滅亡し、残るはアルフレッド大王のいたウェセックス王国のみでした。
ウェセックス王国が覇権を握り、イングランド全土を統一することで「イングランド王国」が成立したのは 927年です。
その後、11世紀になると再びヴァイキングのデーン人(デンマーク人)によるイングランド侵攻が勢いを増しました。
このときのイングランド王は無思慮王(アンレディ)と呼ばれていたエゼルレッドです。
エゼルレッドはデーン人に対抗するために、フランスのノルマンディ公リシャールの妹エマと結婚することで同盟を結びます。
これにより、イングランドはアングロ・サクソンによる王権勢力と、ヴァイキングのデーン人、そしてノルマンディ公の軍勢による三つ巴の戦いへと突入していきました。
エゼルレッドがノルマンディ公をイングランドに呼び寄せたことは、後に大きな禍をもたらします。
フランスのセーヌ川下流の南岸を占めるノルマンディ公国は、スカンディナヴィア半島やユトランド半島(デンマーク)出身のヴァイキングであるノルマン人によって建てられた公国です。
ブリテン島がヴァイキングの襲来によって荒らされていた頃、フランスも同じ状況にありました。困り果てたフランス王はヴァイキングの首領を正式に家臣として迎え入れ、ノルマンディ公国を与えることで事態の収拾を図ったのです。
そのノルマンディ公と同盟を結んだエゼルレッドは、まさに無思慮な命令を下します。イングランド領内にいたデーン人達を皆殺しにせよと……。
戦いはあっても、それなりに共存していたアングロ・サクソンとデーン人の仲を、この命令が切り裂きました。
追われるデーン人たちはオックスフォードの街に逃れ、救いを求めて聖堂に駆け込みました。しかし、神の慈悲はなく、聖堂ごと焼き払われ、悲憤の死を遂げています。
この知らせを聞いたデンマーク王スヴェンは怒り狂い、大軍を率いてイングランド王国に押し寄せました。スヴェンの報復は過激なものでした。有無を言わせずオックスフォードの街ごと焼き払ったのです。
デーン人の怒りのすさまじさに怖じ気づいたエゼルレッドは、平和金と称して大金を差し出すことと引き換えに領内からデーン人を撤退させることに成功します。
しかし、無思慮な命令を発端に多くの領民の命が失われたことで貴族に恨まれ、妻の実家であるノルマンディ公国に亡命する羽目に陥りました。
残された貴族たちが王として迎えたのは、なんと敵であったはずのデンマーク王スヴェンでした。力関係から見て、いずれ征服される定めにあったことから、自ら王として迎え入れることで保身を図ったものと考えられます。
スヴェンの死後、後を継いだのは次男のクヌートです。その間、王位をめぐりクヌートが長男と揉めていた隙を突き、いつのまにかエゼルレッドがイングランドに帰還し、再び王位に就きました。
1015年、クヌートはデンマークの大軍を率いてロンドンを襲います。その最中にエゼルレッドは息絶え、貴族の大半はクヌートをイングランド王として迎え入れました。
こうしてクヌートはイングランド王・デンマーク王・ノルウェー王を兼ねた王として即位します。デーン朝の誕生です。
ここで重要なことは、クヌートは戦闘によってイングランド王国を征服したものの、純粋に力による征服ではなく、あくまでイングランド王国の貴族たちの要請を受けて国王に就いたことです。
そのため、クヌートは征服者として振る舞うのではなく、従来から仕えていた貴族たちとの協調を重んじました。
しかし、1035年にクヌートが亡くなると、内紛によってデーン朝は崩壊し、1042年にはサクソン人のエドワード(懺悔王)が王となり、再びアングロ・サクソン人の王朝が復活します。
それからまもなくして、イギリス史上、そして英語史上においても最大の受難となる事件が起きるのです。
この続きは次回にて。