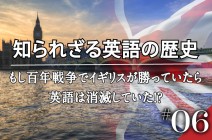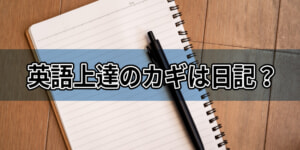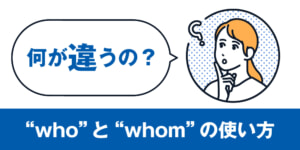【英語の歴史#5】イギリスの公用語が英語からフランス語へ!?ノーマン・コンクエストの衝撃

前回はヴァイキングとして襲来したデーン人とアングロ・サクソンが共存を始めたことで、古英語と古ノルド語が融合し、古英語が大きく変わったことを紹介しました。
→【英語の歴史#4】ヴァイキング襲来!古英語はどう変化していったのか?
今回は英語史を語る上で最大の受難となったノーマン・コンクエストを中心に、中英語の劇的な変化についてたどってみます。
1.ノーマン・コンクエストとは何か
一時はデーン人からイングランド王国を取り戻したアングロ・サクソンですが、その王権は長く続きませんでした。
エドワード懺悔王が子供を残すことなく亡くなったため、誰が王位に就くのかをめぐって騒動が起きたからです。
エドワード王の遺言によるとして、王の臣下として今でいう総理大臣のような役を務めていたゴドウィンの子であるハロルドが王位に就くことになったものの、ハロルドの弟がこれを不満とし、反乱軍を起こしました。
一方、エドワード王とは血縁関係にないハロルドが王位を継ぐことに疑問を呈し、自分こそが継承権をもつと主張したのが、ノルマンディー公ウィリアムです。
エドワード王の母は、ウィリアムにとって大叔母にあたるだけに、二人の間に血縁関係があることは明らかです。
また、エドワード王はデーン人から逃れるために20年ほどノルマンディー公国に亡命していたため、ウィリアムとは親しい仲でした。その当時、王位を譲ると約束されたと、ウィリアムは主張しました。
ウィリアムの優れたところは、単に主張するだけではなく、用意周到に根回しを行ったことです。当時、絶大な力をもつローマ教皇アレキサンドル二世がウィリアムの主張を認めたことは、カトリック教会から正式にお墨付きをもらったも同然でした。
神聖ローマ帝国皇帝ハインリッヒ四世も中立の姿勢を鮮明にすることで、事実上、ウィリアムのイングランド王継承を後押ししたのです。
1066年、満を持してウィリアムはブリテン島南部に大軍を率いて上陸しました。
孤立無援となったハロルドは、それでも良く戦い、弟の起こした北方の反乱軍を打ち破ると、すぐさま南下し、ヘイスティングスでウィリアムを迎え撃ちました。
戦いはハロルドが優勢でしたが、ウィリアムが敗走すると見せかけ後退したところ、ハロルド軍が陣形を崩してまで深く追いかけたことが仇(あだ)となり、機敏に反転したウィリアム軍に取り囲まれ、たちまち敗勢に転じました。
ハロルドは矢に当たって戦死を遂げ、この天下分け目の戦いはウィリアム軍の勝利に終わったのです。
その後もイングランド土着の貴族たちは、ウィリアムと戦い続けました。しかし、ついにロンドンは陥落し、この年のクリスマスにウィリアムは戴冠式をあげています。
それでもアングロ・サクソンの抵抗はまだ続き、ノルマンディー公ウィリアムによってイングランドがようやく平定されたのは、その5年後です。
ノルマン人ウィリアムによる、この一連のイギリス征服を「ノーマン・コンクエスト」と呼びます。
ノルマンディー公ウィリアムはフランス国王の家臣です。しかし、同時にイングランド国王も兼ねるという歪(いびつ)な支配構造が生まれることになったのです。
振り返れば、前回紹介したように無思慮王エゼルレッドが安易にノルマンディ公をイングランドの地に呼び寄せたことが、この悲劇の始まりです。
ノーマン・コンクエストはイギリスにとって他民族に征服されるという屈辱の歴史です。同時にそれは、英語消滅の危機でもありました。
2.書き言葉としての英語の消滅
すでに紹介したように、イングランド王国は過去にデーン人のクヌート王に征服された歴史があります。しかし、クヌート王による征服とノーマン・コンクエストでは、その衝撃度がまったく異なります。
クヌート王の場合は、先王であったエゼルレッドがあまりにも無能、無思慮であったために、代々の先王に仕えてきた貴族たちにも見放され、むしろ多くの家臣に譲位が歓迎された面がありました。
このあたりの感覚は日本人である私たちにはなじみがありませんが、中世のヨーロッパでは王位を他国の親類に譲る事例がしばしばあり、王だけが外国人に取って代わることは、さほど珍しいことではなかったのです。
しかし、ノーマン・コンクエストではアングロ・サクソン系貴族も、クヌート王以来のヴァイキング系貴族も最後まで抵抗を続け、戦い抜きました。そのため、ノーマン・コンクエストは完全に武力による制圧となりました。
そのことは、王だけではなく、支配層が丸ごと変わることを意味しています。既存の貴族は没落し、新たにイギリスの貴族となったのはノルマン人たちです。
この新しい身分関係は、現代にも受け継がれています。イギリスには貴族院があることからもわかるように、今でも貴族がいます。イギリスでもっとも格が高い貴族とされるのは、今も昔も伝統的にノルマン貴族です。
貴族が入れ替わると、貴族に付き従う騎士も入れ替わります。さらに商人も入れ替わり、支配層も経済の実態もノルマン人が握ることになりました。
さらに、大修道院の修道院長もノルマン人へと入れ替えられ、まさにイギリスの実権は、ノルマン人の手に落ちたのです。
では、ノーマン・コンクエストは英語史には、どのような影響をもたらしたのでしょうか?
英語史における最大の問題は、新たに支配層となったノルマン人の用いる言語がフランス語だったことです。
そのため、イギリスの公用語は英語からフランス語に改められ、上流階層の用いる言語は、話すときも読み書きでもフランス語一色に染まりました。
ノーマン・コンクエストからおよそ300年間、征服者の言語であるフランス語こそが宮廷においても、議会や法廷においても用いられたのです。
宗教界も同様で、話すときはフランス語、書き言葉としてはラテン語が用いられました。
一方、小地主や農民、農奴などの下層階級には変化はありません。公用語がフランス語に変わり、上層階級がフランス語を話したところで、庶民の暮らしが変わるはずもなく、相変わらず英語しか喋れません。
英語は上層階級がひしめく表舞台からは姿を消したものの、下層階級の話す言葉として生き残ったのです。ただし、当時の下層階級の人々はイギリスに限らず、話すことはできても読み書きはできないのが一般的です。
日本人は明治前後からすでに農民や車夫に至るまで文字の読み書きができましたが、世界の常識から照らせば間違いなく異常な光景でした。近代に至るまで世界各国とも庶民の識字率は驚くほど低かったのです。
そのため、話し言葉としての英語は残ったものの、書き言葉としての英語は、この時期にほぼ消滅しています。
しかし、現代英語への道を切り開く上で、実はこのことは幸いしました。
英語史では1100年頃より「中英語」の時代を迎えます。中英語ではどのような変化が起きたのでしょうか?
3.庶民が求めた英語の簡略化
一般的に言語は、話し言葉は容易に変わっていくものの、書き言葉は変化を嫌うという特質をもっています。言葉を文字として表すためには正しい綴りを用いるとともに、標準的な文法の順守を求められるからです。
そのため、書き言葉に権威が与えられている社会では、話し言葉にしても書き言葉の制約を受けるため、緩やかに変化することはあっても急激に変わることはありません。
ところが、ノーマン・クエストによって書き言葉としての機能を失った英語は、こうした従来からの制約から自由に解き放たれることになりました。
庶民の間でしか使われない話し言葉としての英語は、庶民の扱いやすいように変わっていったのです。文法が複雑な言語よりも単純な言語の方が、扱いやすいに決まっています。庶民は何事も簡単なものを好む傾向にあります。
こうして庶民の間で、英語の文法は次第に簡略化されることになりました。
まず大きく変化したのは、単語に設けられていた性が、きれいさっぱり消え失せたことです。古英語には現代のドイツ語と同様に単語ごとに性が割り当てられていたため、いちいち覚えるのが大変でした。
そこで、こんな面倒なことはやめてしまおうと、中英語からは単語ごとの性が消えることになりました。それとともに、形容詞の変化もごく簡単になっています。
名詞の複数形も単純になりました。古英語では名詞の複数変化が複雑でした。たとえば、「足」を表す foot の複数形は feet ですが、これは古英語から残った数少ない例外の一つです。
中英語の時代に、ほとんどの名詞の複数変化は改められ、語尾に-sを付けるだけですむようになりました。
動詞も同様です。現在のドイツ語でも動詞は複雑に変化します。古英語の動詞も不規則に変化するものが数多くありました。不規則に変化する動詞は、覚えるだけでも面倒です。
そこで、ほとんどの不規則動詞が規則動詞に改められました。動詞の過去形と過去分詞には、-edをつけるだけで使えるようにしたのです。
現代英語にも take‐took‐taken のように不規則変化する動詞は残っているものの、ごくわずかです。
庶民が望むままに複雑な文法を廃し、より自由に簡略化されたことで、中英語は大きな変化を遂げました。そのため、中英語の時代に英語とドイツ語はかなり異なる言語へと変化することになったのです。
4.二重言語が生んだ英語特有の言葉
ノーマン・コンクエスト以来、イギリスの上層階級はフランス語を話し、下層階級は英語を話すことになりました。これを「社会的二重言語」といいます。
この結果として、英語には独特の変化が起きました。よくあげられるのは、食肉に関する言葉です。
英語では動物の名前と、その動物の肉が食卓に並んだときの名前が違いますが、不思議に思ったことはありませんか?
たとえば牛は ox(オックス)ですが、牛肉は beef(ビーフ)です。飼っている豚は pig(ピッグ)ですが、豚肉は pork(ポーク)です。飼育されている羊は sheep(シープ)ですが、羊肉は mutton(マトン)です。
このような使い分けは、他の言語にはほとんど見られません。英語と同じゲルマン語派に属するゲルマン語にも、このような例は見られません。
ゲルマン語でも日本語同様に「肉」という言葉の前に動物の名前を置くことで、牛肉や豚肉を表します。
でも英語では、厳格に使い分けています。飛行機に乗ったときに beef or pork ? と聞かれることはあっても、 ox or pig ? と聞かれることは絶対にありません。
この英語の独特の言い回しは、二重言語の時代があったことが大きく影響しています。実は beef や pork、mutton などはフランス語、ox や pig 、sheep などは英語です。
その理由は、動物を捕まえたり飼育するのは下層階級に限られるため、下層階級の用いた英語がそのまま残る一方、それらの肉を食すのは上層階級に偏ったため、上層階級の用いたフランス語がそのまま残ったからです。
このように社会的二重言語の時代を過ごしてきたがゆえの痕跡(こんせき)は、現代英語にもたしかに残されています。
5.フランス語からの借用
二重言語の時代が続いたため、英語にはフランス語から借用した言葉が大量に入り込みました。その数は、およそ1万語といわれています。そのうちの7500語は、現代英語でも使われています。
フランス語から多くの言葉が英語に入ったことにより、英語は世界でも有数の語彙数を誇る言語になりました。
フランス語からの借用がはじめに起こったのは、下層階級の間でした。なにせ上層階級はフランス語しか使いません。彼らに仕える下層階級は英語しか使えません。
この状態でコミュニケーションをとるには、下層階級の人々が必要最低限のフランス語を覚えるよりありません。
たとえば、baron「貴族」、noble 「貴族たち」、dame 「奥様」、 servant 「召使い」、 messenger 「使者」などの言葉です。
また統治を表す言葉は、ほぼフランス語からの借用です。government「政府」、royal「王様の」、parliament 「議会」、tax 「税」、mayor 「市長」等々。
フランス語からの借用は多くの分野にわたっています。ことに政治・法律・軍事・経済に関する言葉が多い傾向にあります。army 「陸軍」、 navy 「海軍」、 peace 「平和」と war「戦争」もフランス系です。
食に関しても充実しています。
grape 「ブドウ」
orange「オレンジ」
lemon「レモン」
cherry「チェリー」
peach 「桃」
などの果物の名前
spice「スパイス」
herb「ハーブ」
mustard「マスタード」
などの調味料
roast「ロースト」
boil「ボイル」
fry「フライ」
stew「シチュー」
salad「サラダ」
toast「トースト」
などもフランス語から入ってきた言葉です。
他にも贅沢な料理が出る場合は dinner 「正餐」、 supper 「夕食」といったフランス系の言葉が使われ、さほどご馳走が出ない場合は breakfast 「朝食」のような英語がそのまま使われています。
ノーマン・コンクエストによってフランス語と英語の二重言語の国になったイギリスですが、表舞台から遠ざけられていた英語が、やがって復活の日を迎えます。いったい何が起きたのでしょうか?
この謎は次回、追いかけてみます。