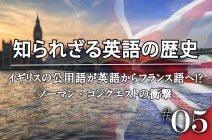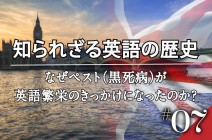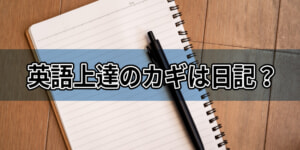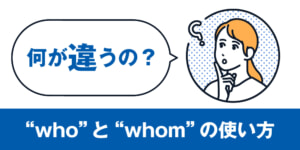【英語の歴史#6】もし百年戦争でイギリスが勝っていたら英語は消滅していた!?

ノーマン・コンクエストによる英語の変化について前回は紹介しました。
→【英語の歴史#5】イギリスの公用語が英語からフランス語へ!?ノーマン・コンクエストの衝撃
今回は下層階級のみで通じる言語とされた英語が、どのようにして復権したのかを見てみます。
1.英語の変化がもたらしたプラス面とマイナス面
ノーマン・コンクエスト後、王権は安定し、繁栄しました。1154年にヘンリー二世の代になると、父母の領地と妻の領地を併せることでフランス全土の3分の2を支配しています。
フランス国王の家臣であるヘンリー二世が、フランス国王よりも広大な領土を有し、同時にイギリス王でもあったわけです。
これを境に、英語に借用されるフランス語にも変化が起きました。ノーマン・コンクエスト後にノイマン人が話していたのは、正確には「ノルマン・フレンチ」と呼ばれるフランス語の方言です。
しかし、ヘンリー二世以降はパリのフランス語である「セントラル・フレンチ」が英語に影響を与えることになります。
面白いのは、ノルマン・フレンチとセントラル・フレンチでは元は同じ単語でも発音と綴りが異なることがあり、その両方が英語に借用されているケースがあることです。
たとえば、catch と chase です。catch はノルマン・フレンチから、chase はセントラル・フレンチから借用されました。現代英語では catch は「捕まえる」、chase は「追跡する」で意味が少し違いますが、両者の語源は同一です。
同様に、cattle「牛」はノルマン・フレンチ、chattel 「動産」はセントラル・フレンチから入ってきた言葉です。warden 「番人」はノルマン・フレンチ、guardian 「保護者」はセントラル・フレンチです。どちらも語源は同じです。
このように、中英語ではフランス語やラテン語から多くの語を借用したため、類義表現が豊かになりました。英語という言語が微妙なニュアンスの違いを表すのに適しているのは、そのためです。
その一方、マイナス面もあります。意味の上では関連があるのに、それが語形に反映されない言葉が、他の言語に比べてはるかに多いのです。
たとえば犬を表す dog は、「犬小屋」や「犬歯」を表すときに使われてもよさそうなものですが、「犬小屋」は kennel、「犬歯」は canine tooth です。
その理由は、英語の dog ではなく、ラテン語の canis「犬」を語源としているためです。
同様に、「目」を表す eye は、眼科医や眼鏡屋を表す際には、ほぼ用いられません。「眼科医」は一般には oculist、「眼鏡屋」は optician です。
意味上は明らかに関連があるにもかかわらず、語源が異なるためにまったく異なる言葉が当てられており、複雑さを増しています。
これは外国語として英語を学ぶばかりでなく、ネイティブが語彙を覚える際にも障害になっています。
ついでに、前回は下層階級の間で英語が簡略化された歴史をたどりましたが、このことでもたらされたマイナス面についてもふれておきます。
それは、語順に関する規則が逆に厳しくなったことです。
古英語では動詞の語尾がさまざまに変化しました。過去形か現在形かの時制はもちろん、直説法なのか仮定法、命令法なのか、さらに主語の人称や数によって複雑に姿を変えました。
そのため、文中の語の役割については、語尾を見れば容易に理解できました。
ところが中英語では語形変化がシンプルに簡略化されたため、文中の語の役割がよくわからない弊害を生むようになりました。どの言葉が主語で、どの言葉が目的語なのか、区別することが難しくなったのです。
そこで中英語以降は、語順によって語の役割がわかるように改められました。動詞の前に来るのが主語、動詞の後に来るのが目的語といったように、語順が固定化されたのです。
現代英語が語順を重視するのは、このためです。
2.悪王がもたらしたイギリスの夜明け
ヘンリー二世の在位は35年に及びますが、そのうちイギリスにいたのはわずか15年です。大半はフランスで過ごしていました。
こうした状況はヘンリー二世だけではありません。歴代の王はイギリスよりもフランスに愛着を覚え、フランスでの暮らしを好みました。
これではイギリスの文化が衰退し、英語がますます軽んじられるばかりです。王がこんな有様では、王に付き従うノイマン貴族にしても似たり寄ったりです。自分たちがイギリスに属しているのか、フランスに属しているのか、曖昧な状況が続いたのです。
しかし、ジョン王が即位すると変化が起きます。ジョン王と言えば、イギリスの3大悪王の一人です。
ジョン王は「欠地王」と呼ばれています。その由来は、父であるヘンリー二世が息子たちに相続させる領地を早くから決めていたため、末っ子であるジョンには、もう相続すべき土地がなかったためです。
ところが兄たちが早くに亡くなったため、ジョンがフランスの広大な領土とイギリス王を受け継ぐことになりました。
ジョン王の転落のきっかけとなったのは、ひとつの恋でした。とあるフランス貴族の屋敷を訪れたジョン王は、12歳の少女イザベラをひと目見て、恋に落ちます。
しかし、イザベラにはすでにリュジーニャンという貴族の婚約者がいました。それでもジョン王はあきらめきれず、イザベラを力ずくで略奪すると、無理やり結婚したのです。
これに怒ったリュジーニャン一族はフランス王に助けを求めました。周辺の貴族たちもジョン王の行動に憤り、ジョン王非難に回ります。
かくしてフランス王は兵を挙げ、ジョン王のもつフランス領に攻め入りました。この戦いに敗れたジョン王は、ノルマンディーを含めたほとんどのフランス領を失う羽目に陥ります。
イザベラという一人の少女へ寄せた恋慕が、イギリス王をフランスから切り離し、イギリスだけの王へと押し込めたのです。
これを「1204年の事件」と呼びます。ジョン王の愚かさが、広大なフランス領土を失うという結果を招きました。
しかれども、何が結果的に幸いするかはわからないものです。「1204年の事件」は、イギリスにとってはプラスに働きました。
ノーマン・クエスト以来、イギリスとフランスが曖昧に溶け合うことで、イギリス人であるという帰属意識がイギリスから失われていました。
ところが、「1204年の事件」でイギリスとフランスが異なる国家として切り離されたため、急速にイギリス人としてのアイデンティティが芽生えることになったのです。
ノイマン貴族も同様です。これまでノイマン貴族の多くはイギリスにもフランスにも領土をもっていたため、フランス王とイギリス王の両方に忠誠を誓ってもかまわないとされていました。
しかし、1204年以降は、こうした二重忠誠は禁止されました。フランス国王に忠誠を誓うのであればイギリスの領地を捨てるよりなく、イギリス王に忠誠を誓うのであればフランスの領地を捨てるよりなくなったのです。
イギリス王に専念することになったジョン王は、その後も悪政を続けました。
なんとかフランスの領土を取り戻そうと軍を起こし、そのたびに貴族たちに重税を課したため、ついに我慢できなくなった貴族たちは、1215年にあるものをジョン王に押し付けました。
それが、「大憲章」(マグナカルタ)です。貴族や市民の権利を明文化し、王の権限に制限を加えた大憲章は、その後のイギリス立憲制の支柱になっていきます。
ジョン王という愚かな国王による悪政があったからこそ大憲章が生まれ、その後イギリスが世界の覇権を握る礎になったのです。
オックスフォード大学にて欽定現代史の教授を務めたウィリアム・スタブスは、ジョン王に対して「悪王必ずしも悪王ならず」といった名言を残していますが、まさにその通りですね。
「1204年の事件」でイギリス人としての意識が強くなったことは、英語の復権に向けて貴重な足がかりとなりました。
3.百年戦争が目覚めさせた国民意識
社会の片隅に追いやられていた英語が復活し、イギリス人の母語として定着する直接の原因となった出来事は、主として二つあります。
ひとつは1337年から1453年まで続いたイギリスとフランスとの戦争、いわゆる「百年戦争」です。
もうひとつは、1350年頃から流行したペスト(黒死病)のパンデミックです。
まず百年戦争ですが、この戦争の発端は、イギリス国王エドワード三世が、フランス王位の継承権を主張してフィリップ六世に挑戦状を発したことです。
ちなみにイギリスとフランスの戦争とはいっても、当時はまだ封建制の時代であり、近代の主権国家同士の戦争とはまったく違います。百年戦争の本質は封建領主による領地争いであって、イギリスとフランスの国民同士が戦ったわけではありません。
また、イギリスにとって幸いだったことは「1204年の事件」によって海外の領地を失ったことで、島国になったことです。そのことは、イギリスに繁栄をもたらしました。
百年戦争をはじめ、その後の戦争はヨーロッパ大陸を舞台に行われたため、イギリスの国土が傷つけられることが、ほとんどなかったためです。
国土が無傷だったからこそイギリスは立憲政治を成し遂げ、後の産業革命によって経済力豊かな国へと成長できたのです。このことも、イギリスの世界制覇が「1204年の事件」を原点にしていることの理由の一つです。
百年戦争において当初イギリスは快進撃を続けました。豊富な略奪品を前に諸侯は大いに盛り上がりました。
しばしの休戦を挟んだものの、イギリスの連戦連勝は続きます。ついにヘンリー五世がフランス王を兼ねることが決まり、イギリスの勝利が定まったかと思われたとき、フランスに一人の救世主が現れます。
オルレアンの少女ジャンヌ・ダルクです。神のお告げがあったとして突如、フランス軍に現れたジャンヌ・ダルクは、まだ少女の身でありながらも兜に身を包み、白馬にまたがって軍旗を捧げ、傷ついた兵たちを鼓舞しながらイギリス軍の精鋭に向かって突撃を敢行しました。
そのとき、奇跡が起きます。圧倒的に不利だったフランス軍がイギリス軍の包囲網を破り、七ヶ月ぶりにオルレアンを解放に導いたのです。
その後も重要な戦いの勝利にジャンヌは貢献し、次々に劣勢を挽回していきました。これによりイギリス王ヘンリー五世ではなくシャルル七世がフランス国王を継ぐことになり、戴冠式が行われました。
ジャンヌもこの戴冠式に出席し、その名声はフランス中にとどろきました。
しかし、ジャンヌはイギリス軍との戦闘中に捕らわれ、ついに捕虜の身となります。当時は捕虜といっても、身代金を支払うことで身柄の引き渡しを求めることが一般的でした。
貧しい農民の出であるジャンヌの身内に、身代金を用意できるはずもありません。本来であればシャルル七世が救出に動いてもよさそうなものですが、なぜか一切介入していません。結果的にジャンヌは、フランスから捨てられたのです。
ジャンヌは神託を受けたと語ったことを理由に異端審問にかけられ、死刑判決を受けました。多くの観衆が見守るなか、オルレアンの奇跡の乙女ジャンヌ・ダルクは火刑に処され、息絶えました。
ジャンヌの死は悲劇ですが、ジャンヌの登場が百年戦争の結果を変えたことは間違いありません。イギリスは勝利を目前にしながら、ジャンヌの率いるフランス軍に一転して負け続け、そのまま戦争は終わりました。
結局のところ、大陸に残ったイギリスの領土はカレー港のみでした。イギリスの領土拡大の夢は、くじかれたのです。
ここにも歴史の if があります。もし、ジャンヌ・ダルクという一人の少女がいなければ、どうなっていたでしょうか?
実は英語が世界の共通言語に成り上がる上で、ジャンヌは大きく貢献しています。なぜなら、もしジャンヌが現れなければ、イギリス王がフランス王を屈服させ、イギリスとフランス両国の王を兼ねたことでしょう。
そうなれば、英仏両国の公用語となったのは、間違いなくフランス語です。やがてフランス語の勢いに押され、英語はいよいよ消滅していたかもしれません。
百年戦争でイギリスが勝利を逃したことは、英語にとっては幸いしました。
さらに英語にとって好都合だったことは、百年戦争によって領土以上に大切なものがイギリスに残ったことです。
それは、フランスとの戦いのなかで育った国民意識です。それを「愛国心」と呼ぶこともできます。
近代国家が成立する上で、国民意識は不可欠なものです。イギリスは確実に近代国家への道を歩き始めたといえます。
国民意識の高揚は、英語の復活を後押ししました。フランスと戦っている以上、フランス語は敵性語です。敵性語であるフランス語を用いることをやめ、イギリスの母語である英語を使おうとする動きが、上流階層の間でも次第に高まっていったのです。
そして、英語復活への最後のダメ押しとなったのがペストのパンデミックです。
次回は「英語の歴史」シリーズの最終回です。パンデミックから近代英語の発展、そして英語が国際共通語になるまでの流れを一気に追いかけてみます。