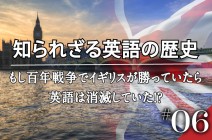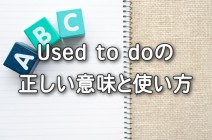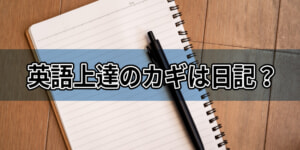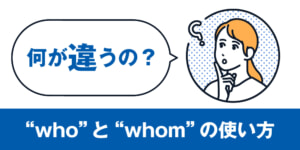【英語の歴史#7】なぜペスト(黒死病)が英語繁栄のきっかけになったのか?

上層階級はフランス語、下層階級は英語を話すという二重言語の国になったイギリスにおいて、英語がどのような過程を経て復活したのかを前回の記事『なぜ英語は復活したのか』にて紹介しました。
→【英語の歴史#7】なぜペスト(黒死病)が英語繁栄のきっかけになったのか?
「英語の歴史」シリーズの最終回となる今回は、ペストのパンデミックから始まり、英語が国際共通語にのし上がるまでの流れを追いかけてみます。
1.パンデミックがもたらした英語の復権
百年戦争の最中、1350年頃からヨーロッパを襲ったペスト(黒死病)のパンデミックは、多くの人命を奪いました。その死者数は、ヨーロッパ全土で2000万~3000万人とも言われています。当時のヨーロッパの人口の3分の1から3分の2に匹敵する、おびただしい数です。
イギリスでも多くの犠牲者がでました。当時のイギリスの人口は約400万人ですが、そのうちの150万人ほどがペストで亡くなったといわれています。
現代と比べて交通が発達していない中世において、全国的に猛スピードでペストが広がった原因は、ペスト患者が出た町では「すぐに逃げろ、急いで遠くに行け」といった対策が取られたためと考えられています。
避難する余裕のある人々の多くは田舎へと逃れていきました。しかし、避難する人々のなかには、すでにペストに感染している人も多く含まれていました。
そのため、避難の道中で多くの人々に感染が広がるとともに、それまで感染者のいなかった町へ新たにペスト菌を運ぶことになったのです。
大がかりな人の移動がパンデミックを引き起こすことは、新型コロナによって私たちも経験しています。
中世ヨーロッパにおいては、衛生状況が劣悪な下層階級ほど、多くの死者が出ました。
ようやくパンデミックが落ち着いてきた頃、イギリス全土を襲ったのは深刻な労働力不足です。
パンデミックによって労働の担い手の多くが死んでしまったため、畑や家畜の世話をする人がいません。これでは、農業が成り立ちません。
以前は肥沃な農地だったのに、パンデミック後は村ごと打ち捨てられることも珍しくありませんでした。イギリスだけで1000ほどの村が消えたと伝えられています。パンデミックは人命ばかりではなく、社会そのものを崩壊させたのです。
しかし、悪いことばかりではありません。深刻な労働不足が、労働者の地位向上を招いたからです。なにせ貴族にしてみれば領有する農園で働いてくれる労働者がいないと、経済的に困ってしまいます。
パンデミック前は「働かせてやっている」立場にいた貴族たちは、パンデミック後は「働いてもらっている」立場へと変わりました。この立場の違いは大きく、完全に労働者の売り手市場となったのです。
労働者の価値が高まるとともに、英語の地位もまた向上することになりました。下層階級で占められた労働者はすべて、フランス語を話せない生粋のイギリス人だったからです。彼らは英語しか話せません。
つまり、労働者の地位向上は、英語しか話せないイギリス人の地位が上がったことを意味しています。
イギリス人の地位向上にともない、地方自治体の担い手も土着のイギリス人へと移り変わりました。やがてタウンやシティといった数多くの地方自治体が誕生します。そこで使われる言語は、当然英語です。
こうして、下層階級のみの言語だった英語は、次第に表舞台へと引き上げられていきました。
やがて1362年には、議会の開会式にて、ついに英語が用いられます。さらに法廷でも、審理においても判決においても英語を用いるように改められました。
ノーマン・クエストから300年近い時を経て、立法と司法の場に英語が戻ってきたのです。
さらに1399年には、ノーマン・コンクエスト以来初めて英語を母語とする国王としてヘンリー四世が即位しました。
その後も英語の復権は順調に続き、1489年には議会においてもフランス語を使わないように改められました。これにより、イギリスの国語の座を再び英語が取り戻すことになります。
支配者であるノイマン人が用いるフランス語に一時は隅に追いやられ、消滅の危機を迎えた英語ですが、およそ4世紀の時を経て、歴史は再び英語をイギリスの母語へと押し戻したのです。
2.「大母音推移」によって生じた発音とスペリングの矛盾
英語史の上では、英語が復権を果たした後の1500年頃から「近代英語」の時代に入ります。
近代英語では標準的な言葉、標準的な表記がなされるようになりました。中英語の時代は庶民の間で話し言葉としての英語が発展したため、地方ごとに方言が多く、スペルもさまざまでした。
方言が乱立する状態を改め、標準的な英語へとまとめていく上で大きく貢献したのは印刷革命です。
15世紀にドイツ人のヨハネス・グーテンベルクが活版印刷術を発明して以来、イギリスでの印刷地であるロンドンでは大量の印刷物が出回るようになりました。
その際に用いられるのは、ロンドン英語のスペリングです。これによりロンドン英語こそが標準英語と定められ、近代英語は一気に発展します。
ことに大きな変化は、15世紀から17世紀にかけて起きた大母音推移( the Great Vowel Shift )です。
「大母音推移」とは、強勢をもつ長母音に大規模な音変化が起こる現象を指します。
具体的には母音の「ア」が「エ」に変化したことで、「エ」が「イ」になり、「イ」が「エイ」になり、さらに「オ」が「ウ」に変化する、というように音の発音がずれていくことです。
「大母音推移」が起きたことで、現在の英語の発音になったのです。
たとえば、name は中英語以前では「ナーマ」と発音されていましたが、「大母音推移」後は「ネーム」と発音されるようになりました。
同様に、home は「ホーメ」から「ホーム」に、take は「ターケ」から「テイク」へ、feet は「フェート」から「フィート」へ、moon は「モーン」から「ムーン」へと変化しました。
発音の変化とともにスペリングも変わるのが、15世紀までの流れです。ですから、発音の変化にあわせて柔軟にスペリングを変えさえすれば、綴りのままに発音するだけで事足ります。
ところが、16世紀からはそれができなくなりました。活版印刷の発明により、「大母音推移」が起きる前にスペリングが固定されたためです。
そのため、発音だけが大きく変わり、スペリングは発音が変わる以前のものがそのまま使われる、という矛盾が生じることになりました。
現在もその状態が続いています。その結果として、初学者ばかりでなくネイティブスピーカーでも発音に頭を抱えることになりました。ネイティブであっても初めて目にする単語は、ネットや辞書で調べて発音を覚えるのが一般的です。
なお大母音推移がなぜ起きたのかをめぐってはさまざまな説があり、未だに本当のところはわかっていません。
ペストのパンデミックによって知識階級がいなくなり、庶民の使っていた発音がそのまま一般的になったともいわれていますが、ひとつの説にすぎません。
実は日本語でも母音の変化が過去に起きたとする説があります。日本語の母音といえば「あいうえお」の5文字ですが、奈良時代以前は、8つの母音が使われていたとされています。ただし、これには学術的な反論もあります。
謎を多く含む母音変化ですが、もし、大母音推移が起きた後に活版印刷が発明されていたならば、現在とは状況が大きく変わっていたはずです。
英語の発音とスペリングの矛盾がなくなり、どの単語も簡単に正しく発音できたでしょうね。
グーテンベルクも、まさか活版印刷が英語の発音を難解にするとは、思ってもいなかったに違いありません。
3.近代英語における借用
イギリスでは、ヨーロッパ大陸よりも遅れてルネサンスが始まります。およそ16世紀頃からです。他のヨーロッパ諸国と同じく、ルネサンス期ではイギリスでもギリシア・ラテン古典研究が盛んとなり、大量の古典語が英語に入ってきました。
この時期に英語に借用されたラテン語は、約1万語といわれています。しかし、難解な言葉が多かったこともあり、現在も使われているのは、その半分ほどにすぎません。
一方、ギリシア語は現在でも新たな科学・専門用語として英語に取り入れられています。
biotechnology「生物工学」をはじめ、biohazard「生物危害」、biocycle「生物サイクル」に用いられる bio- はギリシア語のbíos「生命」に由来します。
ecology「生態学」、ecosystem「生態系」などに用いられる eco-も、ギリシア語の oîkos「家、居住」に由来しています。
大陸との交渉も活発になったことで、フランス語ばかりでなく、オランダ語、イタリア語、ドイツ語などのヨーロッパ近代語からの借用も増えました。
さらに、ヨーロッパばかりではなく、北米大陸やインド・中国の言葉も英語に借用されるようになります。
そのきっかけとなったのは、1588年にイギリス海軍が当時「無敵」といわれたスペイン艦隊を、アルマダの海戦にて破ったことです。
これ以降、帝国主義を推し進めたイギリスは、世界各地を侵略し、次々に植民地化していきます。1600年には東インド会社を設立し、アジアへの侵略を開始しました。17世紀初頭にはアメリカ大陸への移民を始め、18世紀以降はアフリカやオセアニアを支配下におきました。
ついに20世紀初めには、世界の4分の1をイギリス大英帝国が占めることになったのです。世界はイギリスのことを「日の沈まぬ帝国」(the Empire on which the sun never sets)と呼びました。
それら植民地化した地域から、多くの言葉が英語へと流れ込みました。これを「グローバルな借用」と呼びます。
多様な言語から多くの借用を受けて、英語のボキャブラリーは現在のように膨れ上がり、豊かな表現力を獲得したのです。
しかし、イギリスが世界の覇権を握るとともに、この流れは逆転します。英語は、借用する側から借用される側へと立場を変えたからです。
このシリーズの第2回目で紹介したように、現在では科学や医学を含むさまざまな学問で生じる新しい単語のほとんどが英語です。
日本語でも日々、新しい言葉が入ってきますが、その大半は英語をカタカナ表記したものです。
英語で新たに生成された言葉が、今日の世界各国の言語に数多く借用されています。
英語がこのように強くなった背景には、イギリスの覇権が大きく影響しています。
4.英語はなぜ国際共通語になったのか
アジアやアフリカ、カリブ海でイギリスの植民地となった地域では、英語の使用が強制されました。英語が軍事力を背景に世界各地に広がったことは否定できない事実です。
今回のシリーズの冒頭でもふれたように、言語とは民族にとっての魂です。もともとあった言語を禁じられ、英語を強制されたことに対する反発は、もちろんありました。
ですが、植民地から解放された後も、英語を公用語として用いる国が大半を占めています。
その理由の一つとして、多くの国が多民族で構成されているため、ある民族の言語を公用語にしてしまうと他の民族の反発を買い、国家が分断される恐れがあるためです。
多民族で構成される国家になった原因が、そもそもイギリスの植民地政策に求められるケースも存在します。
別の原因として教育の問題をあげられます。英語の教科書を自国の言語に改めるためには、翻訳しなければならない単語が無数にあり、現実的ではないのです。
たとえば数学の場合、日本であれば「素数」なり「因数分解」なりの翻訳された言葉がすでにあるため、英語に頼ることなく日本語のみでたやすく教科書を作れます。
しかし、数世紀にわたってイギリスの植民地支配を受けていた国では、このような実績がないため、今から一つひとつの用語を自国の言葉に置き換える作業が必要です。
これでは翻訳だけで1世紀は要するかもしれません。つまるところ、はじめから英語で学んだ方が、よほど現実的です。
植民地から開放された国の多くは英語に対する反感を抱きながらも、やむを得ない事情から英語を使い続ける選択を下したのです。
こうして現在では、母語ではないものの、教育機関や議会、公共放送などで英語を公用語として用いる国が、インド・シンガポール・ナイジェリアなど70カ国以上に及んでいます。
第二次世界大戦の結果として植民地の独立が相次ぎ、イギリスは強国の地位を失いました。しかし、英語がすたれることはありませんでした。
英語にとって何より幸運だったことは、軍事力を背景にイギリスに代わって世界の覇権を握ったアメリカもまた、英語を母語とする国であったことです。
イギリスからアメリカへと世界の覇権は移っても、英語こそがもっとも重要な言語であることになんら変わりありません。
こうして今や英語は過去に例がないほど世界中の多くの人々が用いる言語となり、国際共通語としての地位を不動のものとしています。
高名なイギリスの英語学者ランドルフ・クワークは、英語を評してこう言いました。英語こそは「日の沈まぬ言語」であると……。
新型コロナウイルスのパンデミックにより、世界全体が急速にネットワーク社会となった今、国際共通語としての英語の果たす役割は、ますます大きくなっています。
英語は今後も、人類にとって必須の言語として広がっていくに違いありません。やがて世界中の人々が、誰でも英語を用いてコミュニケーションをとれる日が来るかもしれませんね。
ここまで、ゲルマン語のひとつの方言にすぎなかった英語が、まさに世界を制覇するまでの歴史について、英語史を交えながらたどってみました。
英語は時代とともに常に変化してきました。もちろん今、この瞬間も、英語は少しずつ変化しています。
英語の果てしなき物語は、これからも永遠に続いていきます。この先はどんな物語が綴られていくのか、なんだかワクワクしませんか!?