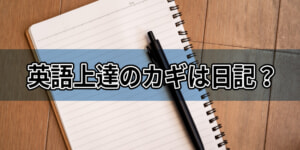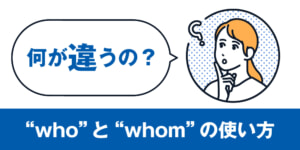「ラディッシュ」は海外で通じない?「大根」の英語表現を紹介!

日本では身近な食材として知られている大根ですが、英語で何と言うか知っていますか。
この記事では、大根の英語表現はもちろん、大根を使った料理や慣用句に関する英語表現も紹介していきます。
英語での表現の仕方を通じて、文化の違いを感じ取れることも興味深いポイントです。
この機会に、英語を学ぶだけでなく、日本と海外で異なる食文化についても知識を深めてみてはいかがでしょうか。
関連記事:
ピーマンは和製英語で通じない!「ピーマン」を英語ではどう言うの?
なす(茄子)は英語で何と言う?なす料理や調理法の表現も一緒に覚えよう!
大根は英語でどう言う?

英語圏では、「radish」という単語で大根を表しています。
しかしながら、英語圏で親しまれている大根と、日本で一般的に普及している大根は全く異なる野菜のため、注意が必要です。
英語圏における大根、つまり「radish」とは、赤くて丸いカブのような野菜を指しています。
日本でもサラダなどで使われていることが多いため、「radish」と言えばこの小さな赤カブをイメージする人が多いのではないでしょうか。
ちなみに、「radish」は「根」を意味するラテン語「radix」を語源としてできた語です。
日本で馴染みのある白い大根を英語で表現したい場合は「Japanese radish」や「Daikon radish」などといったフレーズを使います。
「Japanese radish」は「日本の大根(ラディッシュ)」という意味合いです。
一方「Daikon radish」という表現では「Daikon(大根)」と日本語がそのまま用いられています。
「Sushi(寿司)」などと同じように「Daikon」という日本語がそのまま海外でも使われているのです。
なお「radish」を使った単語の中には「horseradish」というものがあります。
これは、「西洋ワサビ」のことを指した単語です。
辛味と酸味を持ち、日本の本わさびとはやや異なります。
ローストビーフやステーキなどの西洋料理に添えられていることが多い食材です。
「大根おろし」「たくあん」大根料理の英語表現を覚えよう!

大根を使った料理には、様々なものがあります。
日常生活で使う英単語を覚えて、表現の幅を広げていきましょう。
<大根おろし>
まずは「大根おろし」です。
「大根おろし」は、英語で「grated radish」もしくは「grated daikon radish」と表現します。
「grated」は「擦る」「こする」という意味を持つ動詞「grate」の過去分詞形です。
ここから「すり下ろされた大根」、つまり「大根おろし」のことを意味する表現となりました。
大根おろしは和食に登場することが多いですが、洋食と組み合わせる場合もあるため、知っておくと食事を説明する際などに役立つでしょう。
<たくあん>
また、漬物の「たくあん」は、英語で「yellow pickled radish(黄色い大根の漬物)」と言います。
「pickle」は「漬ける」という意味の動詞で「pickled」はこの単語の過去分詞形です。
その他には「pickled daikon radish(大根の漬物)」という表現が使われることもあります。
<つま>
「つま」も、大根を使った料理の一つです。
大根を千切りにしたもので、刺身に添えられていることが多いです。
この場合、英語では「shredded radish」という表現を使います。
「shredded」は「千切り」を意味する動詞「shred」の過去分詞形です。
日本語の「シュレッダー」をイメージすると分かりやすいでしょう。
その他に「garnish」も「つま」を意味する単語として知られています。
「garnish」は動詞では「添える」、名詞では「付け合わせ」や「つま」という意味です。
<切り干し大根>
最後に、和食の定番として知られている「切り干し大根」は、英語で「dried strips of daikon radish」と言います。
細長く切った大根を乾燥させて作るため「dry(乾かす)」や「strip(細長い一辺)」といった単語が使われています。
「大根役者」「大根足」大根を使った日本の慣用句は英語でなんと言う?

日本語には「大根」という言葉を使った慣用句やフレーズがあります。
<大根役者>
まず、代表的なものとしては「大根役者」が挙げられるでしょう。
「大根役者」は、演技が下手な役者を指して使われる表現です。
その由来は諸説ありますが、そのうちの一つに、配役を変える際の「降ろす」と大根おろしの「おろし」をかけたという説があります。
役を降ろされてしまうほど演技が下手な役者という意味ですね。
英語では「下手な役者」という意味で、「poor actor」や「bad actor」といった表現を使います。
また、口語的な表現として「ham」「ham actor」が使われる場合もあります。
「ham」は「ハム」や「豚のもも肉」という意味です。
こちらにも諸説ありますが、由来の一つとして、「ham」が「道化者」の意味を持つ所から来ている説があります。
自然な演技ができない下手な役者は、道化者のように見えることから「ham actor」と呼ばれるようになったそうです。
<大根足>
「太い脚」を揶揄する言葉として、「大根足」という比喩的表現があります。
英語にする場合は「太い」という意味の「thick」を用いて「thick legs」と言います。
<大根の年夜>
その他には「大根の年夜」という慣用句が有名です。
「大根の年取り」「大根の年越し」と言われることも。
これは、旧暦10月10日の十日夜(とおかんや)のことを指しており、この日には大根畑に入ることを忌む習わしがあります。
収穫祭の一種のため、英語にする際は「harvest festival called “daikon no toshiya”(”大根の年夜”と呼ばれる収穫祭)」などといった表現が当てはまるでしょう。
<大根注連>
やや聞き慣れないかもしれませんが、大根という言葉を使ったフレーズの中には「大根注連」というものもあります。
これは「だいこんじめ」と読み、神棚などに飾られている、太めの七五三縄(しめなわ)のことを指しています。
七五三縄にはいくつかの種類があります。
その中で、大根のように一方が太く、反対側にかけて次第に細くなっていくものを「大根注連」と呼んでいるのです。
英語の場合は「a sacred rope with tufts of straw named “Daikonjime”(”大根注連”と呼ばれる藁の房から成る神聖な縄)」などの表現を使うと伝わりやすいでしょう。
「sacred」は「神聖な」という意味を持っており「a sacred rope」で「神聖な縄」、つまり七五三縄のことを指しています。
なお「tuft」は「房」、「straw」は「藁」という意味の単語です。
まとめ:大根の英語表現を通して海外の人とのコミュニケーションを楽しもう

和食は海外でも人気が高く、最近では「Daikon」のように、日本語でそのまま表現して伝わる食材や料理があるほど。
しかし今回紹介した「Japanese radish」など、食に関する様々な英語表現を知っておくと、日本の文化や食事をより丁寧に、詳しく紹介することができるでしょう。
海外の人とのコミュニケーションもさらに楽しめるようになります。
インプットした知識はどんどんアウトプットし、定着させていきましょう。
QQEnglishでは、公式LINEで英語学習に役立つ情報を定期的に配信しています。
公式LINEに登録すると「オンライン英会話の無料体験レッスン」が、“合計3回も受けられる特典”をもれなくプレゼント中です!
英語学習のインプットをした後は、ぜひこの機会に英会話のアウトプットも行いましょう!