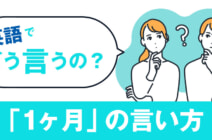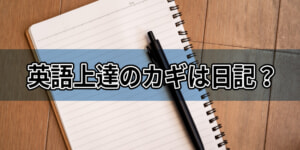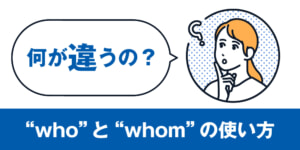ゼミの英語は何?アメリカでもゼミはあるの?アメリカの大学事情を解説!

日本ではよく耳にする「ゼミ」。4月からゼミに所属する大学生の皆さんも多いのではないでしょうか。日本では、ほとんどの大学生がゼミ(理系の方は研究室)に所属して卒業論文に取り組みますよね。
アメリカでは、どうなのでしょうか?
アメリカの大学事情に興味のある方、将来アメリカへの大学進学や留学を考えている方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
「ゼミ」関連の使える英語
まず、英語で、ゼミにあたる単語と、関連して使える単語を見ていきましょう。
Seminar (ゼミに近いもの)
日本語のゼミに1番近いものが、このSeminarになります。
ちなみに、英語での発音は「セミナー」。
ゼミの元になった読み方はドイツ語読みからきています。
日米ではこのゼミという形式以前に、大学での研究のあり方がそもそも違いますので、直訳しても通用しない点に注意です。
細かい点は後述します。
Lecture (講義)
日本でもお馴染みの「講義」形式の授業のことで、教授が一方的に授業をする形式のものです。
比較的大人数に対応した授業です。
Recitation (小規模クラス)
直訳すると「朗読」「暗唱」などと訳されますが、大学においては、講義を補助する形の、参加型の授業を指すことが一般的です。
問題を解いたりディスカッションしたりする事から、あえて日本語を当てはめるならば「演習」に近いと思います。
Lectureとセットになっている事も多く、アメリカの大学のシラバス(授業計画)で「Lecture and Recitation」という形の表記を見る事もあるでしょう。
アメリカには「ゼミ」はない!?
さて、アメリカで一般的な授業形態について触れてきましたが、今度はより深く、大学の体制について触れてみましょう。
そもそも卒論は必須ではない
日本の大学は1〜2年(もしくは1〜3年)まで一般科目を受け、その後ゼミに所属して教授の指導を受けながら卒論を完成させていく、というのが一般的な流れだと思います。
これに対してアメリカの大学は、そもそも卒論が卒業には必須ではありません。
学科によってはSeminarに所属をして論文を書くことが必須のところもあるようなので確認は必要ですが、基本的には必要な単位を取りきれば卒業資格を得られます。
Seminarとゼミは似て非なるもの
選択できる授業の形態の一つにSeminarがあり、先ほども触れましたが、ここに所属をすれば論文を書く事になります。
Seminarの形式も、日本のように教授の指導があるわけではなく、教授と一緒に、所属している学生同士のディスカッションやプレゼンを通じてテーマへの理解を深めていく、という形式が一般的です。
そのため、黙っていても教授の指導がもらえる日本のゼミと違い、アメリカのSeminarは自分から積極的に発言をし、自分から情報を取りに行かないと、なかなか情報や学びは得られないでしょう。
その他の授業や決まりも日本とは違う
単位についても、日本のように3年でほぼ全ての単位を取得し、4年生はあまり学校に来ない、という事は起きません。
なぜなら、アメリカは各学年毎に取得できる単位が設定されているからです。
そのため、日本では馴染みはないかもしれませんが、アメリカの学生は4年生になってもしっかりと学校にきます。
また、授業も日本と比べると課題もたくさん出て、その難易度も高い傾向にあります。
よく、アメリカの大学は出るのが大変、と言われますが、その理由の一つがこれです。
課題に困っているときやゼミで壁にぶち当たった時は、日本のように指導教官に質問、というわけにはいかないので、友達に聞くのが1番の対策になります。
以下に周りの友達を巻き込み、苦手なところを補完し合えるかどうかに、充実したアメリカでの大学生活が送れるか否かが決まると言ってもいいでしょう。
その他、ゼミなどで使える英語
それでは、最後にゼミに関係する、使える英語をいくつか紹介しようと思います。
いずれもアメリカの大学生活においては、何度も出てくる基本的な単語なので、しっかりと押さえておきたいですね。
Syllabus (シラバス)
日本語に当てはめると、「授業計画」となります。
授業をとった際に一番初めに配られるもので、授業に関する情報が詰め込まれた書類です。
そのため、何度も読み返すことになります。
Compulsory Subject, Elective Subject (必修科目、選択科目)
必修科目と選択科目はCompulsory Subject、Elective Subjectと表現します。
取得単位は学年を上げるために非常に大切なので、この情報は逃したくないものです。
必修科目はMandatory Course、選択科目はOptional Courseと表現されることもあります。
Assignment (課題)
授業をとると必ず出される課題はAssignmentといいます。
日本の大学のように過去問が出回るということはまずないと思った方がいいので、友達と一緒に真剣に取り組む姿勢が求められます。
Handout (配布資料)
授業の際ほぼ確実に配られる配布資料はHandoutと表現します。
Assignmentをこなすための補助資料にもなりますので、授業の際は重要な存在になります。
Credit (単位)
授業を履修した際に得られる単位はCreditと表現されます。
イギリスの大学ではUnitという表現を使う場合もあるようです。
例えばスペイン語の授業で3単位が得られる場合は、We can get 3 credits for the Spanish class.と表現します。
Professor (教授) / Facilitator (進行役) / Teaching Assistant (アシスタント)
科目の重要になってくるのが、それらを担当するProfessor (教授)や、SeminarやRecitationの進行役になることも多いFacilitator (進行役)やTeaching Assistant (アシスタント)の存在です。
Discussion / Debate (議論、討論)
アメリカの大学のゼミに参加する際には議論や討論が行われることがセットになることがほとんどです。
自由に議論を交わす場合はDiscussion、特定のテーマの賛成反対に別れて意見を戦わせるものはDebateとなります。
Critical Thinking (批判的思考)
議論や論理をより深く、多角的に理解するということも、アメリカの大学のゼミに参加している限りはついて回ると考えた方がいいです。
そういう概念はCritical Thinkingと呼ばれ、日本語では批判的思考と訳されます。
まとめ
今回はゼミの英語訳をはじめ、アメリカでの大学の授業体系の一部について触れてきました。
日米の大学の違いについて、興味深い点もあったかと思います。
将来アメリカへの大学進学や留学を考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。